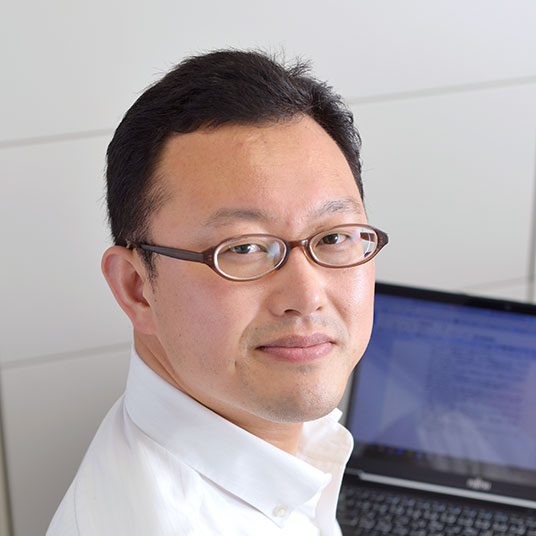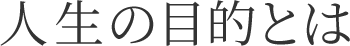(第1回はこちら)
(前回の内容はこちら)
ガラス細工のMVP

荒川俊介は、かつてのトップ営業マン足立涼平が突然飲みに誘ってきたことに、胸がざわついていた。
このところ会社でもほとんどすれ違ってばかりだ。
それでも、不安を押し隠して自然に振る舞おうとしていた。
会社から少し離れた居酒屋の、奥まった個室で向かい合う。
飲み物と料理が運ばれてきた。2人とも黙ったままだ。いや、これまでなら足立が次から次へと話題を差し出すのだが、今日はむっつりと押し黙っている。
最初に運ばれてきた料理の皿が空になった頃、俊介が沈黙を破った。
「珍しいよね、こうして夜に誘ってくれるのって」
「まあ、ね」、どうも歯切れが悪い。
「でもよかったよ、誘ってくれて。ゆっくり話したかったから」。俊介は親愛の情を込めたが、足立は宙をにらんだまま、目を合わせようとしない。
ようやく思い切ったように、ビールを一気に飲み干して言った。
「俺、3月末で退職するわ」
俊介は息をのんだ。その予感がなかったわけではない。しかし同時に、長年の仲間が去ろうとしていることが、にわかに受け入れがたかった。
「有給消化があるから、出社は3月1週目までだ。どうもどうも、お世話になりました」
足立はふざけた顔をして頭をぺこりと下げてみせた。
「もう決定?」
「うん。昨日、加藤課長に話した」
「加藤課長、何て言ってた?」
「何も言わなかった。というか、何か言いそうだったけど、俺、そのまま出てきたから」
俊介は、加藤課長の胸中を思うと、胸が締め付けられるようだった。
「僕は言わせてもらうよ」、俊介は真正面から足立を見据えて言った。
「どうして辞めるんだよ。辞めるなよ。営業がいやなら、異動願いを出せばいいじゃないか。制作だって面白いよ。デザイナーさんもライターさんも、うちのパートナーさんはいい人ばかりだし……」
「俊介、俺は、辞めるんだ」。話し続けようとする俊介を、足立がきっぱり制した。
「人ってさ、働くことで何か大事なものをすり減らすんじゃないかな……。お前も気をつけろ。突然来るんだよ、こういうのって。数字を追いかけて、スーパーマン演じて、もう疲れたよ」
「でもそれは、数字だけを追いかけていたからだろ? もっと生きる目的を見つめろよ。僕は『歎異抄』を読んでわかったよ。生きる目的はあるんだ、本当の幸せになれるんだ、仕事は、そのための大切な手段なんだよ、足立」
「……俊介が勉強会のまとめをLINEでくれているから、そのことは理解したよ。理屈は面白いと思ったし、頭ではわかるよ」
でも感情は違う、と言うように足立は顔をしかめた。
「だけどな、1回こうなったらもうだめだ。サラリーマンなんて、もううんざりなんだよ。この間、南砺市の新規就農の説明会に行ってきた。農業とか、そういう人生もありかなって思う。でもまあ、しばらくは休憩するわ。疲れたんだ、俺は」
足立に退職を思いとどまらせるための言葉が、俊介の頭に浮かんでは消えた。だが、何を言っても拒絶されるだろう。きっと加藤課長も同じ気持ちだったに違いない。
「そっか」、うつむいて顔をしかめることしかできなかった。「その話を聞けただけでも、誘ってもらえてよかった」と力なく微笑んだ。
「それだけじゃねえぜ」、足立は身を乗り出して、通りかかった店員に3杯目のビールをオーダーした。たしか足立は、あまり酒が強いほうではない。今日はピッチが速い。
「俊介に、言いたいことがあるんだ」
矛先が自分に向いた。俊介が身構える。
「俺は、仕事で自分をすり減らしてきた。やればやるほど、スカスカになっていくんだ。MVPでちやほやされても、何の足しにもなりゃしない。自分がどんどん嫌なやつになっていくんだよ。営業トークはばっちりだ、商品知識もすげえ詰め込んでる、広告効果の上げ方もわかる。俺が受注したらお客さんは喜ぶんだ。足立さんが担当でよかったって。だけど、俺はそうは思わない。これで何十万、積んだ。ただそれだけだ……。
月曜から金曜まで突っ走って、土日は家でDVDを観るか、1人でドライブに行くか、女の子とデートするかして、何とか気持ちを紛らわせる。また月曜から自分をすり減らすんだ。だけどお前は……」、足立は運ばれてきたビールをぐいっとあおった。どう考えても飲むペースが速すぎる。
「だけどお前は違う。お前は仕事で自分をすり減らしていない。客が喜んだらお前も心から嬉しそうだ。俺はね、そういうお前が大っ嫌いだったんだよ」
いきなりの攻撃に、ショックのあまり俊介は呆然としたままだ。
「俺、よく昼飯にお前を誘っただろう。前回は確か秋頃だった。何でだかわかるか?」
俊介は無言で首を横に振った。
「あの日、俺は午前中に大きな仕事を取った。それで気分が良くてな、自慢したかったんだよ。あの頃俊介は目標未達が続いて落ち込んでいただろう。そんなお前に、自分の能力を見せつけたかったんだ。案の定、お前は俺をまぶしそうに観て、自分のことを卑下してしょんぼりしていたな。それが観たくてわざわざ誘ったんだよ」
足立は嘲笑しながら続けた。
「お前がしょぼくれてるのを見ると、俺のエネルギー値が回復するんだよ。俺は、そういうやつなんだ。でもな、それもアホくさくなってきたわ。はい、ゲームオーバー。全部ただのゲーム。それも終わりだ」
怒りが俊介を突き上げた。珍しく声を荒げずにいられなかった。
「ふざけんな、足立。何がゲームだよ。あのなあ、自分のためだけにエネルギー使ってんじゃねえよ! だからすり減るんだろ! 誰かのためにちょっとは使ってみろよ!」
足立は酔った目をして、ケラケラと笑った。
「ははは。友情でそんなこと言っているのかもしれないけどな、目の前のお友だちは、ただのつくりものですよ~」
「つくりもの?」
「そう。俺、いつも営業会議のときにキャラメルラテ飲んでただろう。上にぐるぐるクリームがのったやつ。あれも俺の姑息な演出なんだよ」
意味がわからず、俊介はただ足立を見つめていた。
「営業会議、いつもピリピリしていただろう。加藤課長がカリカリとタブレットを噛んでいる音を聞くだけで、胃が痛くなるような嫌な空気だ。だから俺は演じたんだよ。わざわざキャラメルラテなんて小道具まで持ち込んで。ボクはカリスマ営業マンだから余裕で~す、営業会議なんてちっとも怖くありませ~ん」
「お前……」、俊介は自分が嫌われていることを知っても、足立の肩を抱いてやりたいような気持ちになっていた。あまりに繊細だった。あまりにガラス細工みたいなやつだ。
「俺はつくりものなんだよ。つくりもののMVPだ。なのにお前は、おどおどしているくせに、いつも自分自身のままだ。ナチュラルだ。泣いたり、笑ったり、お客さんの変化を喜んだり。そういうお前に、無性に腹が立つんだ」
だんだん足立のろれつが周らなくなってきている。俊介は店員に小声で水を頼んだ。
気がつくと店内にはソーラン節がBGMで流れていた。そういえば足立と一緒に会社の忘年会でソーラン節を踊って盛り上がったことがあったなあ、と俊介の脳内には脈絡なく何年も前のことが思い出されていた。
「これ、お前が昔くれたメール。言っただろう、しばらく持ち歩いてたって。覚えてるか」
足立は古くなって傷んだ紙を投げて寄こした。4つ折りにたたまれた白いコピー用紙だった。広げてみると、一昨年の日付だった。
昨日のクレーム大変だったね。いつになく落ち込んでいるようだからおせっかいながらメールを書いてみます。
足立は我が社のスーパースターだから、何でもできる。同期ながら憧れていたけれど、そんな足立にも隙があると知って、不謹慎だけれど、ちょっと親しみを感じたりしています。
あのクレームは市場変化の兆しでしょうね。たしかにお客さんの指摘している視点は、いまの営業4課から欠落しています。1本目の矢が飛んできたのは、単に足立の顧客数が圧倒的に多いから、というだけでしょう。
意外と落ち込みが激しく見えるのは、きっとお客さんに悪いなあって思っているからでしょうか。そう考えると、落ち込んでるところもカッコよく見えちゃうよ。
足立は、毎日カッコいいよ。落ち込んでても、カッコいいよ。
足立は、足立のままでいいんだよ!
俊介
「お前のせいだ」、足立は紙をひったくるように取り返した。「お前がそんなこと言うから、スーパーマンでいなくちゃならなかったんだよ」
3杯目のビールは、半分ほど残ったままだ。俊介もグラスを置いて、足立を見つめる。
「俺はお前を恨んでるんだ、俊介。お前のせいで無理しすぎたんだ」
「そうかもしれないな。悪かった」
「何だよ、ちくしょう、お前のそういうところ、ほんと嫌いだよ」
「え、どういうところ?」
「そういう……、ボサツみたいなところだよ!」
罵られているのにもかかわらず、俊介は吹き出しそうになった。
「菩薩かよ」
「腹立つわ。ほんと、むしずが走るわ、お前」
足立は乱暴に財布から5千円札を抜き出すと、バンッとテーブルの上に置いた。
「あー、すっきりした。むかつくやつに、文句言ってすっきりした」、と千鳥足で店を出ていった。
ゆらゆら揺れる足立の背中を、俊介は愛しいようなせつないような、憎めない気持ちで見送った。
(つづきはこちら)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから