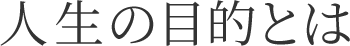こんにちは、おさじまです。
最近友人と電話で話をしたのですが、彼は「職場でも家庭でも自分の役割があって、気がつけばそれをこなすことに一日が費やされてしまってる」と語っていました。
あなたも、そんなルーティンワークのような日常に、ふと「これが私の望んだ人生だろうか?」「本当にこのままでいいのだろうか?」という疑問が頭をよぎることはないでしょうか?
今回は、その答えを求めて納棺師になったあと、一人で世界を旅したある女性の貴重な体験談です。 彼女の見つけた意外な答えとはどんなものだったのでしょう。
死を意識した時、人は生の重みを実感できる
その女性とは阿川幸子さん(仮名・35歳)。
旅した国は、タイ、トルコ、カンボジア、チリ、ボリビア、ペルー、メキシコ、ヨルダン、ベトナムなど15カ国を超えています。きっかけは、ある異色な職業経験からでした。
以下、阿川さん自身が語ったことです。
なぜその仕事を選んだかといえば、進路を考えていた大学3年の時、読んだ『納棺夫日記』の影響でした。
アカデミー賞も受賞した映画『おくりびと』制作のきっかけとなった本で、著者は同じ富山県の人です。
感銘したのは、「死を意識した時、人は生の重みを実感できる」ということでした。
ならば納棺師こそ理想の仕事に思えたのです。
平成20年、結婚式と葬儀を請け負う富山市のセレモニー会社に就職し、上司から希望の部署を尋ねられた時、
「納棺師になりたいんです!」
と即答して苦笑されました。普通、この場面で若い女性なら、「ブライダル部門」と答えるからでしょう。
研修を終えると、早速、葬儀の連絡が入りました。依頼者の家を訪れ、布団に横たわる遺体の血のけのない唇に紅を差す。
「ついさっきまで、息をし、言葉を話していた口だろうに……」
そう思うと、思わず涙が流れました。
しかし、毎日遺体に触れるうち、だんだんその感覚もマヒし、エンバーミング(遺体を消毒や保存処理)などの知識、復元作業や処置の技術を身につけることに力が入り、遺体が単なるモノとしか思えなくなっていきました。
死に化粧を施したぐらいで死んだ人がいい所に行くはずもない。
故人に永遠の別れを告げた遺族の悲しみを癒やすため、と自分に言い聞かせるものの、上司からは、「遺族に高い棺を勧めるように」「葬儀依頼の件数を増やそう」と 営業指導をされ業務に奔走した。
結局、納棺師もただのビジネスに思え、3年で退職しました。
「死ねばオシマイ。ただのモノになる。それなら一度きりの人生、楽しまなきゃ損だ」
そう思って今度は定時で終わる事務職を選び、仕事を終えるとダンスサークルに足を運ぶようになりました。
ですが……
何かを変えたいと世界へ飛び出す
そんなアフターファイブ中心の生活も、初めは刺激的でしたが、だんだん同じことの繰り返しに飽きてきました。
しかし仕事もサークルも、やりだした以上、勝手には休めません。
自分の意志とは無関係に、生活が一つの鋳型にはめられていくようで悶々とするようになりました。
「これが私の望む人生?このまま結婚して、お母さんになって、やがてお婆ちゃんになってそして死ぬ。本当にそれでいいの?」
納棺師をしていた頃、何度も味わった遺体の感触。あれが他人ではなく未来の自分の姿と考えると、このままではむなしすぎると思いました。
何かを変えたい。
変えなければならない。
でも日本にいては何も変えられない。
自問自答の末、日本を離れる決意をしました。
異文化に触れたら、何か大切なものに気づくかもしれない。
行く先は、皆の行かない中東や中南米がいい。未知の世界なら、きっと何かが待っている。
胸ときめかせ、二十代の後半、ペルーの世界遺産マチュ・ピチュや、中東ヨルダンの遺跡・ペトラなど、リュック一つで旅して回りました。
旅のスタイルは「一人、安宿、途上国」。







中でも印象深かったのは、チチカカ湖の旅でした。
ペルーとボリビアにまたがる世界でも稀な古代湖で、大きさは琵琶湖の12倍、標高3810メートルの高地にある。湖には大小41の島があり、様々な先住民族が、漁業や農業で生計を立てています。

(チチカカ湖)
文明社会と全く違う彼らとの生活は、新鮮な驚きの連続でした。
島の一つである「ウロス島」は、島全体がトトラと呼ばれる葦で作った浮き島で、住居やボートの他、学校や病院まで全てトトラです。
家も古くなれば新しいトトラを補充し、家を建て替えるのを深刻に考えません。
彼らにとって住居とは、単に雨風をしのぐ手段でしかないからです。
「日本人なら〃一国一城の主〃とかいって、マイホームは一生の大仕事なのに……」。それまでの固定概念を覆されました。

(ウロス島)
インカ時代のまま、電気もガスもない生活をしているケチュア族の住むタキーレ島にも滞在しました。ジャガイモと手作りチーズ、キヌア(雑穀)のスープなど、質素ながらとてもおいしい。
360度をチチカカ湖に囲まれ、聞こえてくるのはヤギやヒツジ、鳥の声ばかり。子供たちは人懐っこく、キャッキャと笑顔で寄ってきます。
毎日何かに追われ、キュウキュウと働きづめの日本人と比べると、平和で牧歌的なこの国の人々は、肩の力が抜け、ずっと幸せそうに見えました。
「日本では、毎年3万人が自殺している」などと話すとびっくりされます。
きっとここには自殺するような苦しみがないのでしょう。
ならばこの島に永住するのがいいのか?
しかしそれは、気の遠くなるほど退屈なことに思われました。
「幸せって、何?」
本当の幸福を探す旅の道中で、いよいよ迷子になってしまったような気がしました。
祖母のお葬式で聞いたお経をきっかけに……
結局、何一つ確かな答えのつかめぬまま日本へ帰った私に、大好きだった祖母の訃報が届きました。
葬儀の日、読経を聞いていると、何を言われているのか分かりませんでしたが、何かそこに悲しみを癒す慈愛に満ちた教えがあるように感じ、無性に意味が知りたくなったのです。
納棺師をしていた頃、多くの僧侶と接しましたが、お経の意味を教えてくれる人には会えませんでした。そこで、近くの文化会館で行われていた仏教講座に参加してみたのです。
何度か通ううち、「有無同然(うむどうぜん)(※)」というお経の言葉を教わりました。
これは端的にいえば、お金持ちも貧しい人も、皆、苦しんでいるということです。金持ちには金持ち特有の悩みがあり、貧しい人には貧しい人ならでは苦しみがあります。
「熱病の者はどんな山海の珍味も味わえないように、心の暗い人は、どんな幸福も味わえない」とのお話に、まるで、心の底を言い当てられたような気がしました。
心が暗いとはどういうことか?
それは、私たちの100パーセント確実な未来とは暗黒の「死」だからです。
「生きる」とは、その「死に刻々と近づく」ことにほかなりません。
これを仏教では生死(しょうじ)の一大事(※)といい、たとえ世界中の富を集め、権力を手にしても、死を前にしてはその輝きは色あせてしまう。
誰の心の底にも、死への不安の音が鳴り響いている。
燃料が切れれば墜落するしかない飛行機では、乗客はファーストクラスだろうとエコノミーだろうと、誰も空の旅を楽しむことはできません。
同様に、死という大問題をかかえる私たちは、お金や財産、名誉や地位など、有る者も無い者も皆、人生の旅を楽しむことができず、苦しみ色に染まってしまう。そういうお話でした。
体が病気ではどんな珍味も美味しくありません。これまでの人生、珍しい経験はいろいろしてきましたが、心底、幸福を感じられなかったのは、自分の外に原因があるのではなく、自分の内側、すなわち「暗い心」にあったと教えられ、まるで目からウロコでした。
「その生死の一大事は、解決できるのですか?」
恐る恐る講師に尋ねると、
「もちろんできます。しかも平生、現在ただ今です。それが本当の仏教の教えで、『平生業成(へいぜいごうじょう)』(※)といわれるのです」と力強く言われました。
それがどういうことかまだ分からなかったのに、なぜか興奮を抑えられず、「やった!これで私の心の旅は終わった」と心の中で躍り上がったのを覚えています。
それから阿川さんの仏教を勉強する旅が始まりました。
しかし、「今度はあてのない一人旅じゃないんですよ」と笑う。
心の通う友だちがたくさんできたし、仏の教えという最高の道標を手に入れたからと言います。
阿川さんの夢は、旅行で出会った人たちに、本当の仏教の教えを伝えること。
彼女は最後にこう語っていた。
「『袖触れ合うも多生の縁』というでしょう。生と死は全ての人の問題で、世界中がその答えを待っていますから!」
(関連記事)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから