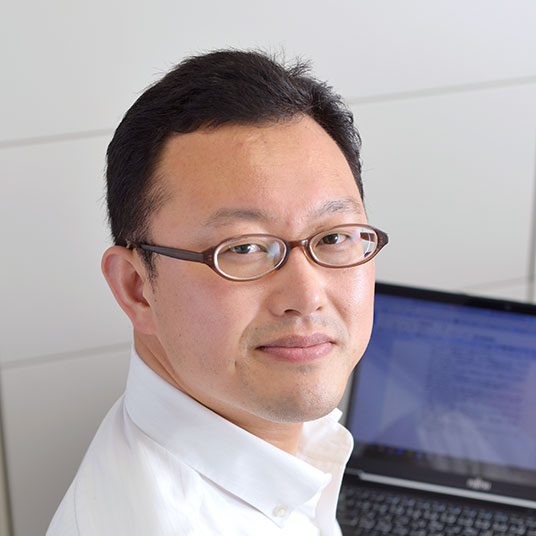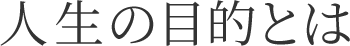(第1回はこちら)
(前回の内容はこちら)
赤城と荒川の再会

再会は突然だった。
11月に入ると、富山の街には木枯らしが吹く。夕暮れどき、研修会社〈フォーユー〉の受付ブザーが鳴った。
総務部のデスクで研修資料の校正をしていた赤城晴美は、軽く咳払いをしてから受付用の内線ボタンを押して受話器をとった。
「はい、総合受付でございます」
「アド・エージェンシーの荒川と申します。アカギ様に、4時半にお約束を頂いております」
「アラカワ様、お待ちしておりました。お掛けになって少々お待ちくださいませ」
晴美はひざ掛けをたたんで立ち上がり、受付へ続くドアの手前にある鏡で身だしなみを確認した。
お客様の前に出るときには全身くまなくチェックすべし、というのが南原社長からのお達しである。
「お待たせいたしました、赤城でございます」
ドアを開け、受付ソファの前に立ちっぱなしの男性を見て、晴美は驚いた。
「アラカワさんって、俊介さんだったんですか!」
「アカギさんって、晴美のこと……でしたか」
晴美と俊介は大学時代、同じサークルに属していた。俊介が2年上で、晴美は後輩に当たる。しかし、今日は俊介が営業する側だ。
思わぬ再会の余韻もそこそこに、応接スペースに通されると俊介は丁寧に切り出した。
「来夏に向けて弊社発行の『マチ・ニュース』紙上で、『この人の講座を受けたい!富山の素敵なセンセイ』という新しい記事広告を企画しており、現在、リサーチをしているところです。そんななか御社のウェブサイトに行き当たり、南原社長の理念や事業内容に惹かれました。おそらくよい先生方を抱えていらっしゃるのではないかと思い、お話を伺いたくご連絡差し上げた次第です」
「広告出稿については社長判断となります」と制しながら、晴美は資料を開いて見せた。
「ただ、研修会社にそういう先生がいるかどうかで言えば、何人かメディア受けしそうな素敵な方がいますよ。たとえば、こちらの五木あかね。オーラのある華やかな方で、弊社のエース講師と言っても過言ではありません」
「ああ、いいですねえ。こういう個性のある先生がありがたいです。読者の興味を引くと思います」。俊介は相好を崩した。
「ならば、こちらの先生はどうですか? エネルギッシュで、受講された方からの評判も高いです」――。
もとは気心の知れた間柄である。打ち合わせは順調に進み、ひとしきり話し終えると、2人はほっと一息、お茶を飲んだ。
改めて、久々の再会を喜び合う。
「いやあ、まさか晴美と会えるとは。元気そうだね」
「まあまあです。俊介さんは広告のお仕事でご活躍なんですね」
「全然、ご活躍じゃないですよ。ずっと制作畑だったんだけど、営業に異動してからなかなか厳しくて。正直まいっていますよ」。かつての仲間の気安さで、思わず弱音を吐いた。
晴美は大きくうなずいた。「私もうまくいかなくて悩んでるんです。この間なんて……」
ドアの外を気にして声のボリュームを下げ、ヒソヒソ声で続ける。
「みんなの前で社長に注意されちゃったんですよ。いったい何年やってるんだ、少しは自分のアタマで考えろって。ひどくないですか」
思わず俊介は笑ってしまったが、晴美の顔は険しいままだ。
「社長のことを第一に考えて私なりに頑張ってきたのに、全然評価されてないんだなって」
「評価されていないかどうかは、また別の話でしょう。期待しているからこそ、厳しく言ってくれたのかもしれないよ」
「たしかに、これまでは少し受け身だったかもしれないって気づきました。単なる指示待ち人間だったつもりはありません。けれど、これからはもう少し能動的に成果を出せるようになりたいと思っています」
「なるほどね、僕たちもそろそろ仕事の仕方や生き方を見直す時期に来ているのかもしれない。具体的にどうしたらいいのかは、悩むところだけれど」
「そうなんです。それで、この間、思い切って『タンニショウ』っていう本を買ってみたんです。初めて古典の棚に行きましたよ」
「へえ、『歎異抄』って、あの日本の名著の?」
「さすが俊介さん、ご存じでしたか」
「うちのトップがよく言っているから、名前だけは。でも何でまた……」
「実は社長に注意されて落ち込んでいたとき、偶然バスの中で聞いたんです。『歎異抄』の話を……。会社の愚痴を言う若者に叔父さんらしき人がアドバイスしていたんですけど、その内容が、まるで私のことを言われているみたいで。もう直感で本屋さんに行って、思い切って買っちゃいました。まだ全然読めてないけれど……」
「なるほどね、僕も直感で動くことがあるのでわかります。よかったら、見せてもらえますか?」
「席にあるので、いま持ってきますね」。晴美は軽やかな足取りで出ていった。
俊介がしばらく所在なげに窓の外を眺めていると、晴美は戻ってくるやいなや、「もう、サイアクです~」とうなだれる。
「社長からいきなり残業って言われちゃいました。明日の研修内容が急遽差し替えになったからって」
「けっこうな量?」
「はい、2時間くらいはかかりそう」
「まあ、仕方ないよね」
「ありえないですよ~。もっと早く言ってくれたら調整できたのに」
「でも、お客さんの都合でしょ?」
「そうですけど……。でもうちの社長、よくあるんですよ、ぎりぎりになって予定変更するとか」
「まあまあ」。唇をとんがらせて怒っている晴美をなだめて、俊介は話を戻した。「それかな?『歎異抄』は」
「はい、そうです。買ってはみたけれど、難しそうで。でも今日こそ、どこかでお茶しながら読もうと思っていたんです」
「それは残念だったね。仕事頑張って。僕もそろそろ次のアポに行くよ」
2人は連絡先を交換し、「また今度」とそれぞれの仕事に戻っていった。
縁は異なもの味なもの

冷気の中を俊介が向かった次のアポイントは、先日オーナーが不在にしていたカフェ「スマイル・ウェルカム」だった。
「失礼します。オーナーのタテヤマ様と6時半からお約束をいただいているんですが」
「あっ、はい、立山です」、立山豊が手を拭きながらカウンターから出て来た。
「『マチ・ニュース』さんですね、よく読んでますよ。すいませんね、この間は不在にしていて」
「ありがとうございます。はじめまして、アド・エージェンシーの荒川と申します」
「2階へどうぞ」
階段を上がると、窓を大きくとった開放的な空間が立ち現れる。壁一面にずらりと並んだ本が圧巻だ。外の白樺がライトアップされている。夜もいい雰囲気だ。
「すみません、他のお客様のお邪魔にならないようにします……」
恐縮そうに俊介が言うと豊が笑った。
「今日はちょっとした修理があって、3時で店を閉めたんです。だから気にしないでください」
豊は奥の部屋からパソコンを持ってくると、窓際のソファ席を打ち合わせの場とした。
俊介が改めて頭を下げる。
「お時間いただきましてありがとうございます。本日は弊社発行のフリーペーパーの広告のご案内で参りました。『マチ・ニュース』を読んでくださっていると先ほど伺い、嬉しく思っております。ありがとうございます」
俊介は媒体資料を広げて、発行部数や媒体特性などを丁寧に説明した。
豊はうなずきながらしばらく聞いていたが、突然、腕を組んでうーんと低い声を出した。
思わず俊介は説明を止めて、豊を見た。
「いやいや、すみません、変なリアクションをしてしまって。荒川さん、説明うまいなあと思ったんです」。豊はポリポリと頭をかいた。
「自分はつい、思いついたことを口に出してしまうタイプなもんで。この店を開業する前も、銀行やら役所やらで、うまく話せなくて苦労しました。保険会社の営業時代も大変でしたが、起業するともっと説明能力を求められるんですよね」
「こんなに素敵なカフェをつくり出す能力がおありなのに」
「好きなことをああだこうだと話すのは楽しいんですよ。でも、いまの荒川さんみたいに、わかりやすく理路整然と説明するのは苦手で……。誰かが整理してくれたらいいんでしょうけど」
俊介はふと思いつき、「もしよかったら、僕からいろいろ質問してみてもいいですか。カフェ『スマイル・ウェルカム』さんについて」と聞くと、豊は「お願いします」と身を乗り出した。
会ったばかりの2人だというのに、すっかり気が合っている。
「ではまず、こちらのカフェのコンセプトを教えていただけますか」
「コンセプトというほどの立派なものはないんですけれど……。元々本が好きなので、ゆっくり読書するスペースがほしいと思っていたんです。あと、松の木がきれいでしょう? コーヒーも、わりと美味しいと思うんです」
思わず俊介はうなずいた。出されたコーヒーは味わい深く、香りも上質だった。
「確かに美味しいですね。何かこだわりはあるんですか」
「以前は生命保険会社の法人営業部で働いていたんです。毎日のように外勤で、アポからアポへ移動する日々でした。合間にちょっと時間があくと、よさそうな喫茶店を見つけてはコーヒーを飲んでいたんです。そのうちに、だんだん味にうるさくなりまして」
「たしかに営業マンにとって、美味しいコーヒーの存在は大きいですよねえ」
「ですよね。コーヒーのドリップはかなり修業しましたよ。知り合いの焙煎所で叩きこんでもらって……、マスターが心を込めて淹れたコーヒーというのを、うちのウリにしていけたらなあと思っています」
「マスターのコーヒー、また飲みに来ますよ。あの本棚の本もじっくり見たいですし」
俊介がにっこり笑うと、豊もつられて笑顔になった。
「本だけは贅沢してきたので、家にはまだまだいっぱいあるんです。大学時代は文学サークルにおりまして、ちょっとした本オタクなんですよ」
「へえ、文学サークルだったんですね。お好きな作家は?」
「ははは。いまだに太宰治だったりするんですよね。古いですか」。豊は照れくさそうに立ち上がると、2杯目のコーヒーを淹れに階下へ降りていった。
「……荒川さん、広告出稿しますのでお願いしますね」。カップを置きながら唐突に言う。
何と1月号から、毎月広告を出したいという。開業時の経営計画に、集客手段として『マチ・ニュース』への広告予算が織り込まれていたのだ。
アクセスの悪いこの店にとって、向こう1年間で経営を軌道に乗せるためには、地元情報誌への広告掲載は必須だった。その媒体として『マチ・ニュース』が最も効果がありそうだという検証もすでに済ませていた。
「毎月掲載してくださるんですか! ありがとうございます!」
「実は来られる前から決めていたんです。他のフリーペーパーも検討した結果、『マチ・ニュース』さん一本で行こうと。とはいえ、実際に荒川さんに会って安心しました」
「営業に来たつもりでしたが、何もしていませんね」
「いやいや、荒川さんはすごく魅力がある広告営業マンだと思いますよ」
「え、本当ですか」
「聞き上手だと言われたことがあるでしょう? 荒川さんの質問に答えているうちに、頭のなかがどんどん整理されてくるんです。つい何でも話したくなってしまう」
「そんな、恐れ入ります。以前は制作サイドにおりまして、取材だけはたくさんしてきたからでしょうか。過分なお言葉ですが、嬉しいです」
「お世辞じゃないですよ、だって、いま何時だと思いますか」
あわてて時計を見ると、もう9時を過ぎていた。立山豊の話を、もう2時間半も聞いていたのだった。俊介自身も時間を忘れていた。
改めて店内を見回した俊介は、オフィススペースのボードに貼ってある1枚の紙に気がついた。何かのチラシのようである。
「『歎異抄』! ちょっと拝見してもいいですか」。前のアポイントで赤城晴美と『歎異抄』の話をしたばかりの俊介は、この展開に驚いた。
「ああそれ、信金の融資担当の方からいただいたんです。それこそ文学サークルのときの先輩なのですが。これからの役に立つだろうって勧めてくれたんです」
「立山さん、『歎異抄』お好きなんですね」
「本好きを自称しながらお恥ずかしいのですが、きちんと読み通したことはないんです。でも、だからこそ、この勉強会に行ってみようと思って」
そのチラシには「『歎異抄』とは」という説明書きが書かれていた。
鎌倉時代に書かれ、貴族や知識階級のものであった仏教を、身分や性別に関係なく万人にひらかれた、親鸞聖人の生々しいお言葉が記されています。
「善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」の1文などは、「あ、日本史や倫理の授業で聞いたことがある!」という方も多いのではないでしょうか。
実は、流れるような美文で知られるとどまらず、深い人間観、死生観を訴えているところに、特徴があるんです。
「幸せになりたいすべての方へ……か」
じっとチラシに見入る俊介に、豊は思わず誘いの声をかけた。
「よかったら一緒に行きませんか。実を言うと、1人で参加するのは少々気後れしておりまして」
「実は、今日こちらに伺う前に知人の会社で打ち合わせがあったのですが、そこでも『歎異抄』の話になったんですよ……」。俊介はくいっと顔を上げた。
「ご一緒させてください。それからもう1人、その知人も誘ってよろしいですか」
「もちろんです」。豊は握手せんばかりの勢いだった。
階段がミシミシと音を立て、金色の短髪をした細身の青年が上がってきた。
「お、拓哉。こちら『マチ・ニュース』さんだ。来月から毎月広告を出すことになったよ。荒川さん、うちのスタッフの林拓哉です」
「林です」。青年は恥ずかしそうに挨拶し、豊に買い物袋を渡すなり、会釈して去って行った。
豊はややバツが悪そうな顔をした。「ろくな挨拶もできなくてすいません。人見知りで……。打ち解けるといい奴なんですけど」
「もともとお知り合いだったんですか?」
「実は昔、文学サークルの後輩集めて、それこそ読書会みたいなことをやっていたことがあるんです。誰かの紹介で来てくれて以来、なぜか慕ってくれているんです。それで開業にあたって声をかけてみたら、手伝ってくれることになりまして」
文学好きの脱サラ起業家と、彼を慕う年の離れた青年。〈カフェ「スマイル・ウェルカム」〉に、荒川俊介は仕事の関わり以上の不思議な魅力を感じ始めていた。
(つづきはこちら)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから