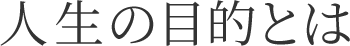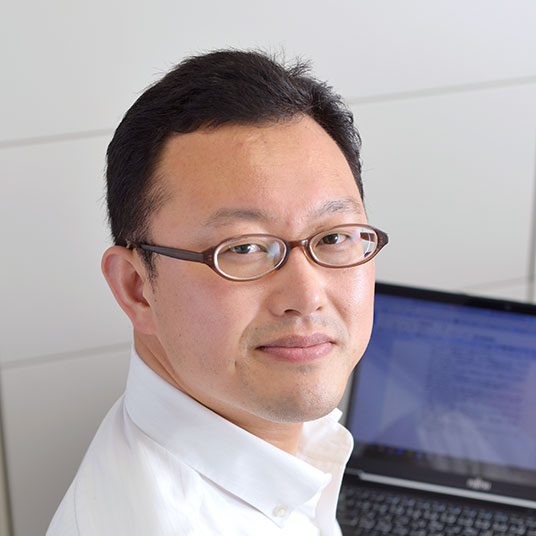
日本の古典『歎異抄』には、人生を、ガラリと変える力が秘められています。
そのことをぜひ知ってほしいと思い、小説形式でお届けします。
晴美の怒り

赤城晴美が『歎異抄』に出会ったのは、突然だった。
その日、晴美はとても強い怒りを感じていた。我慢できないくらい頭に血がのぼっていた。
(もう、無理。社長の発言、絶対に許せない)
10年以上勤めた会社を、いま初めて晴美は(辞めたい)と思っていた。
怒りの原因は、昨日の社長との会話だった。
「あれ、晴美。来月の会場、取れてないぞ」
2週間後に迫った研修の会場が確保されていないことが発覚したのだ。
「えっ。先方の自社ビルでやるのかと思っていました。特にご指示がなかったので」
いつもは明るく温和な社長、南原浩二の目が険しくなった。
「ご指示がなかった? お前なあ……。
先方さん、いつもと違う環境で研修を受けることにメリットを感じていたって話、この前の会議で言っただろ?
そのぐらい気づいてくれよ。俺がいちいち指図することじゃないだろ。
いったい何年、この仕事やってるんだ?
言われなきゃできないなんて、新入社員じゃあるまいし。頼むから、少しは自分のアタマで考えて行動してくれよ」
ずっと仕えてきたボスからのあまりに無神経な言い方に、晴美は大きなショックを受けた。
たしかにその話は記憶にあったが、このところあれこれと忙しく、また特に頼まれたわけでもなかったので、そのままやり過ごしてしまっていた。
晴美が勤めている会社〈フォーユー〉は、社長の南原が一代で築いた研修会社で、来年20周年を迎える。
晴美が大学を卒業し新卒で入社した頃は、まだ所帯も小さく、まさに育ち盛りのベンチャー企業だった。
以来、総務課で社長のサポートから庶務まで、雑多な仕事を一手に引き受ける日々を過ごしてきた。
頼まれた仕事は心を込めて仕上げ、社長に「晴美の仕事は丁寧だな。ありがとう」と言われるのが何よりも嬉しかった。
資料をつくれと言われたら、細部まできちんと指示を仰いで期待通りのものにする。
大切な来客とあれば、事前に先方の顔ぶれや好みを聞いておき、タイミングよくもてなした。
たとえお世辞であっても、「気の利くスタッフがいてうらやましい」「御社のお茶は実に美味しい」と感心されることはよくあった。
これまで社長の指示を一番に思い、少しでも役に立とうと仕事をしてきた。
それというのも、道なき道を切り開く南原を心から尊敬していたからだ。
だからこそ、長年の間、従順に仕えてきた。
それなのに、あんな言い方をするなんて。しかも、みんなの前で……。
一晩寝ても、まだ怒りが収まらなかった。
『歎異抄』って何?

今日は土曜日、仕事は休みだ。こんな気持ちで家にいても仕方がない。町をぶらついて気分を晴らそう。
晴美はコートをひっかけて外へ出た。
富山の10月は、セーター1枚では少し肌寒い。薄手のコートが必要だ。
通りまで出ると、ちょうど富山行きのバスが来るところだった。
いつもは車で移動しているが、何となく今日は、暖房のきいたバスに乗って外を眺めたい気分だった。
(駅前のショッピングセンターをぶらつくのも悪くないな)と、バスに乗り込んだ。
車内を見渡すと、これから結婚披露宴にでも出席するのだろうか、礼服姿の男性2人が並んで座っている。そのひとつ前の座席が、ちょうど空いていた。
早々に腰をおろし、シートに寄りかかってため息をつく。
(ほんとにもう、最悪の社長なんだから……)
頭の中で文句を言っている晴美の耳に、ふと、後ろの2人連れの会話が飛び込んできた。
「ほんとにもう、最悪の社長なんですよ!」
(えっ?)
一瞬、自分の脳内の言葉が声に出てしまったのかと、晴美はびっくりした。
礼服姿の2人は、叔父と甥といったところだろうか、若いほうが年輩の男に、さかんに愚痴をこぼしている。
「うちの社長、超ワンマンなんですよ。人の話なんて、全然聞く気がない。全部自分の思い通りにならなきゃイやなんだ。もう、うんざり」
晴美は思わず、聞き耳を立ててしまった。
「若手は若手で、すっかりやる気なくしちゃって……。雰囲気悪いし、数字もダダ下がりだし、このままじゃ、うちの会社は沈没しちゃいますよ。どうしたら変わってくれますかね」
年輩のほうが、おもむろに口を開いた。
「そうか、大変だな。……お前、『歎異抄』って、知っているか?」
「タンニショー? ああ、日本史の教科書で出てくる、あれですか? 読んだことはないけど、一応、名前ぐらいは」
「そうか、読んでないのか。『歎異抄』には、この世の私たちは深い因縁でともにこの世に生を受けた、友であり兄弟だと説かれているんだ。たとえ、気に食わない人が周りにいても、『袖ふれ合うも多生の縁』といわれるだろう。相手を責めてばかりいては、力を合わせて大事な使命が果たせないとは思わないか?」
その言葉を受けた若いほうは、不服がありそうだ。
「そんなの理想論じゃないですか。いっぺんうちの社長を見てから言ってほしいですよ。ほんと子どもみたいなんですから。思いつきで突っ走るし、無神経だし、社員の都合なんてまったく考えてないし。トップが変わってくれない限り、どうしようもないじゃないですか」
思わず晴美は心の中で大きくうなずいた。(そうそう、無神経よね。うちの社長みたい)
「『歎異抄』は理想論じゃないんだけどな」。年輩の男が諭すように言う。
「だいたい、毎日起きる問題は、昔も今も、変わらないもんだよ。しょせん人間なんだから。そんな状況でどう考えるべきか、何のために生きるべきか、そんな人間にとって大切なことが、『歎異抄』に書かれているんだ」
「本なんか読んだって、うまくいくとは思えませんね」と若者が憤る。「問題は、社長なんです。社長が変わらないとどうしようもない。自分のことが、見えてないんですよ。よく事情も知らないで、僕が変わればいいなんて言わないでくださいよ!」
年輩の男は思わず苦笑した。
「……ほら、お前だって、俺から何か言われたって、目が外ばかりに向いているだろ? 社長だって若手だって同じだよ。みんな、自分のことは、なかなか分からないんだ」
そう言うと、優しい口調になってこう続けた。
「それでも、自分の姿を知る方法はある。『歎異抄』には、『人間は皆、煩悩の塊』だと説かれている。お互い煩悩の塊だと分かってこそ優しくなれるんだ」
(お互い煩悩の塊だと分かってこそ優しくなれる? どういうこと??)
昨日の憤慨が収まらないままだった晴美の気持ちに、うっすら新しい感情が湧いてきた。
(私、何か、大きな勘違いをしていたかもしれない……)
若者は押し黙ったままだ。年輩の男は続ける。
「お前も時間をつくって『歎異抄』を読んでみたらいいよ。気持ちが変わるから」
「でも僕、古典ニガテなんですけど。そんなの、社長が読めばいい」。逆ギレモードは収まったものの、まだ少しすねているようだ。
「確かに古典だけど、時代を超えて変わらない、人生の根源的な問いに答えを示しているんだ。……知りたくないか?」
バスはまもなく富山駅に着こうとしていた。
ターミナルに入る信号待ちで、気の早い乗客が席を立ち始めた。晴美の後ろの礼服の男たちも立ち上がった。せわしない空気に紛れ、2人の会話は聞こえなくなった。
あてもなく富山駅に降り立った晴美の心は、ざわめいていた。さきほどの若い男へのアドバイスが、まさに自分に向けられたもののように感じられた。
(私はこれまで、言われたことはちゃんとこなしてきたし、自分では、それなりに仕事ができると思っていた)
(でも、社長が私に期待していることって、本当は何だったんだろう。私、胸を張って成果を出してるって言える?)
知らない人の会話が、こんなに気になるなんて。何だか不思議に思いながらも、足は駅ビルの上階にある大型書店へ向かっていた。(あの本、探してみようかな……)
あれこれ考えながら歩くうちに、南原社長の発言がまたよみがえってきた。
――少しは自分のアタマで考えて行動してくれよ。
感情的には腹が立っていても、長年仕えた敬愛するボスからの言葉であった。素直になってみると、たしかに、仕事に対して受け身だったかもしれない。
(でもやっぱり、あの言われ方は悔しいな)
思わず、涙ぐみそうになった。
自分なりに頑張ってきたつもりだったのに、評価されていなかった。しかもみんなの前で当てつけるように言われて、これまでの努力を全否定されたような気持ちだった。
(あんなふうに言わなくたっていいのに……もう少し評価してくれたっていいのに)
(私、いったい何のために頑張ってきたのかな)
また苦い気持ちがこみあげてきた瞬間、ふと、年輩の男の言葉が思い出された。
――『袖ふれ合うも多生の縁』といわれるだろう。相手を責めてばかりいては、大事な使命が果たせないとは思わないか?
書店は、にぎわっていた。
晴美はほっとひと心地ついた。昔から晴美は書店が大好きだった。特にこういう大型書店に来ると、何時間いても飽きない。
気ままに書棚を巡り、目についた小説や絵本を手に取り、パラパラとめくる。のんびりとお気に入りを見つける時間は、かけがえのない至福のひとときだった。
今日の晴美は、いつもと違う。これまであまり行ったことのない、古典の棚へまっすぐ向かった。
先ほどバスの中で聞きかじった『歎異抄』という本の解説書コーナーは、あっけないほど簡単に見つかった。棚の2段を使って、ずらりと何十冊も並んでいる。
そのうちの1冊が、くるりと表紙を見せて陳列されていた。晴美は思わず手に取った。
(つづきはこちら)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから