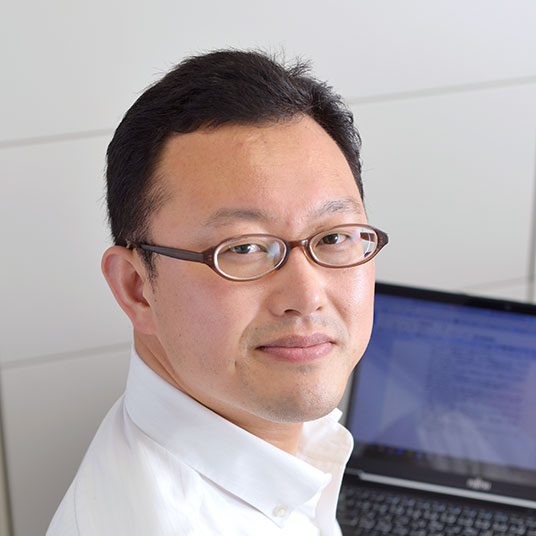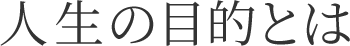(第1回はこちら)
(前回の内容はこちら)
数字を追いかけなかったら、僕の価値って何なんでしょうね

広告代理店〈アド・エージェンシー〉の会議室では、営業四課の月次会議が行われていた。
加藤課長が何十粒目かのミント味のタブレットを口に放り込んで、眉間にしわを寄せたまま、ペンで机を叩いている。
どこか遠くから、年末の楽しげな声が聞こえてくる。
しかし会議室には、賑わう街とはまったく逆の、ドライアイスのような冷たい空気が流れている。
「で、2月号の目標数字に220万円足りません、と」
トップ営業マンの足立涼平は、われ関せずの表情でキャラメルラテをすすっている。
「見込み数字、いまからもっと出せるやついるか」
「あたし、真冬のビューティ企画でネイルサロン当たってみます」
「ロマンチックウィンターのディナー特集、市内のホテルに再アタックしてみます」
「ボクも居酒屋かたっぱしから飛び込みしてきます」――
加藤課長は若手の積極的な声を聞いても、苦虫をかみつぶしたような表情を崩さなかった。
「お前ら、そうやって先月も目標達成できなかっただろう。フリーペーパーは、しっかりとクライアントとのリレーションを深めてマーケットをつくっていかないと、競合とのシェア争いに陥るだけだ」。そう言うと、加藤課長は語気を強める。
「今朝、マネージャー会議でも社長が言っていたぞ、このまま未達が続くようなら、いずれ廃刊だって検討するって」
「……は、廃刊?」
「それって『マチ・ニュース』がなくなっちゃうってことですか」
「富山は、紙媒体でもまだまだ可能性があるって言ってたじゃないですか」
「既存のクライアントさんだって困るし」
「デジタルな広告手段が多様化する時代だからこそ、地域に密着したアナログな広告活動が必要だって」
「お前ら、いいかげんにしろ!」。加藤課長が一喝する。
「これだけのマーケットがあるのに、俺らは苦労しているじゃないか。毎月ひいひい言いながら数字を積み上げて。それでも、ついこの間までは、グループの達成記録を更新していたんだ。ここ2号だ、急に未達になったのは」
そう言って加藤課長はトップ営業マンの足立をじっと見た。
いや、ついこの間までトップ営業マンに君臨し続けていたが、突然、営業数字を積むことができなくなった足立を。
しかし、足立はうつろな目で窓の外を見ている。
「なあ、足立どうした?先月と今月、お前の数字は目標に届かない。それどころか、60パーセント台じゃないか。これは年間契約の分だろ。つまり、新規契約がないってことになる。どうしたんだ?スランプか?」
こういう個人のメンタルに関わる話を、メンバーがずらりと揃う営業会議の真っ最中に、当の本人に聞けるのが、加藤課長の加藤課長らしいところだ。
足立はキャラメルラテを机に置いて椅子に座り直した。
「スランプ……っていうわけじゃないですよ。ただ、ふと気づいちゃったというか、あほらしくなっちゃったというか」
別人のような話し方をする足立をみんな息を殺して見つめている。
「課長、僕が数字を追いかけなかったら、僕の価値って何なんでしょうね」
「は?お前は何を言っているんだ?」
「口八丁手八丁、クライアントから予算を引き出すのが得意な僕って、何のために存在しているんでしょうか」
「何のために存在?ばか言え。社会人たるもの、目の前の仕事がすべてだ。結果を出すまでとことんやる、それで給料をもらっているんだ。子どもじゃあるまいし、どうしたんだ?価値も何も、まずは責務を果たすのが筋ってもんだろう」
「課長はタフですね。こんな数字至上主義の会社で管理職やっているんですもんね。僕はもう、きつくなってきました」。そう言って、ため息をついた。
「お客さんのことが、数字にしか見えない。疲れちゃったんです、そんな自分に」
「……お前の言うことも、わからんでもない。改めてゆっくり話を聞こう。でもな、これだけはみんなにも言いたい。広告営業って、数字を追いかけるだけじゃないんだ」。加藤課長は、真剣な表情で語りかけた。
「たくさんのお客さんが『マチ・ニュース』に広告を掲載してくれることで、『マチ・ニュース』の情報の量と質が高まれば、媒体価値も高まっていく。そうすると読者がついてきて、広告の効果もまた大きくなる。持ちつ持たれつの関係じゃないか。そうやってお客さんのパートナー的存在になっていくんだよ」
会議室は静まりかえったままだ。
「課長」、足立が突然立ち上がる。「アポがあるので失礼します。今日は直帰します」
パタンと閉じられたドアを、加藤課長はただ見つめるだけだった。
会議が終わるやいなや、俊介は足立の携帯に電話をかけてみたが、つながらなかった。
夜、また自宅でかけてみたが、だめだった。留守電に入れる言葉さえ見つからなかった。
俊介は自宅のソファに座り込んで、深いため息をついた。
(足立……いまどんな気持ちでいるんだろう)
黙って会議室を出て行った友の背中が思い出された。
「僕に数字を任せて少し休めよ」、そう声をかけてやれたら、どんなにいいか。
しかし、迫り来る締日を前に、足立のカバーはおろか、自分の目標達成すら危ういのだ。
足立の悩みは、他人事ではない。
俊介にも、顧客が数字に見えることが増えていた。
若いメンバーたちも、やっとの思いで毎月を過ごしている。
創刊以来、みんなで目標数字を追いかけ続けてきたチームに、危ういほつれが出て来たように思われた。
何かをしっかりと整えなければ……。
そう思うものの、整えるべきは何なのか、俊介には皆目見当がつかなかった。
俊介は目を閉じて考えた――。
何か重要なことを見逃している。
それは何なのか。
何をすればよいのか。
出口の見えない、憂鬱な夜だった。
(つづきはこちら)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから