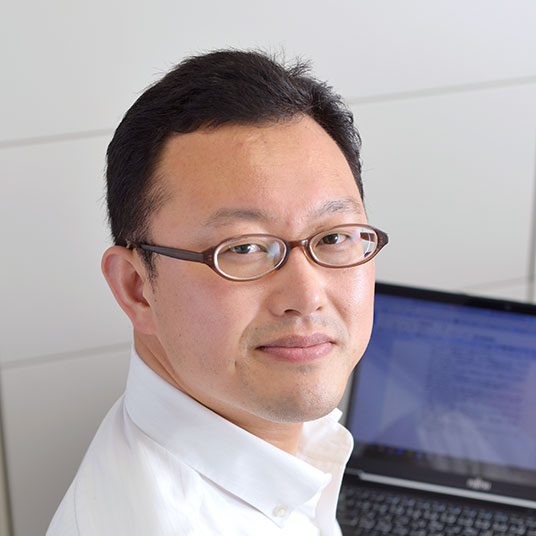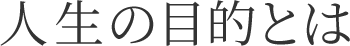(第1回はこちら)
(前回の内容はこちら)
カフェ「スマイル・ウェルカム」

富山の環水公園エリアは、リッチな層が多く居住する地域だ。
そのエリアに住まう人々にふさわしいお洒落なカフェがまもなく開業する。
カフェ「スマイル・ウェルカム」のオーナー、立山豊は大きな段ボール箱を抱えて自宅マンションに戻るところだった。
ポプラ並木が黄色く色づいている。学校帰りの小学生たちが、駆け足で追い越していった。
新卒以来勤めていた保険会社を、豊は半年前に退職していた。
もうすぐ40歳。この機に、念願のカフェを開業したかったのだ。
だが、このご時世に脱サラして起業しようとする豊に、周囲の反応は芳しくなかった。
――そんな好き勝手なことをして。生活はどうするの。瑠華の学費だってかかるのよ。
豊の母親は、孫のことが気がかりで、安定収入を手放す決断に大反対だった。
――開業するやつはごまんといるけど、この業界、そう甘くないぜ。
飲食店を2店舗経営している知人は心配顔だった。
――大丈夫? もって1年ってとこじゃない?
保険会社の元同僚は、豊の送別会で酒の肴に前途を冷やかした。
いや、あれは冷やかしではなく、冷静な意見だったのかもしれない。
法人営業部の面々は、1年ともたず消えていく若き起業家を何人も見てきているのだから。
(俺なりのイメージはあるんだ。どうしても挑戦したい)
自分でも、経験不足で危なっかしいところがあることは理解している。
それでも、この強い気持ちを抑えることはできなかった。
いよいよ来週から営業開始だ。オープンに向けて、10月はてんてこまいだった。しかもお金は出ていく一方だった。
登記の申請に行った。物件を借りた。厨房の工事をした。什器を入れた。壁紙を貼り、家具を入れた。
開業資金が、ざるから水がもれるように、あっという間に消えていく。
早くも想定していた初期投資額をオーバーしていた。
悩みは金銭面だけではない。カフェの開業にこんなにもいろいろな準備が必要だということも、やってみて初めてわかった。
届け出や契約など、毎日が書類の洪水だ。
内外装も手間のかかることばかり。
美味しいコーヒーをハンドドリップで上手に淹れられるようになるまでに、知人の焙煎所に通いながらどれだけ練習したことだろう。
軽食は実家の青果店から仕入れた果物と野菜を使って、フルーツパフェと野菜シチューをつくるだけにしているが、それだって何とか形にするまでに、数え切れないほどの試作を繰り返した。
起業する前は、理想のカフェを思い描くだけでワクワクしていたが、走り出してからは不確定要素ばかりで、ため息をつくことが増えていた。
夢みたいなことばかり言わないでくれる?

自宅マンションに着くと、玄関のドアを開ける前に、豊は大きく深呼吸をした。家族に不安げな顔を見せるわけにはいかない。
「パパ、おかえり~」
小学6年生の娘、瑠華がテレビから振り返って豊を出迎える。
「何か不思議だね。こうして昼間にパパに会うのって」
「そうか?」
「だって残業ばっかりで夜遅かったし、土日もしょっちゅうゴルフに行ってたよね」
ダンスを習っている瑠華は、バレリーナのようなおだんごヘアを最近好んでしている。
今日も上下ピンクの派手なジャージを着て、いまにも踊り出しそうだ。
よく見ると、テレビの画面にはダンスレッスンの映像が映っている。自主練習をしていたのだろう。
「ねえ、パパ。会社やめちゃったの? それともやめさせられちゃったの?」
娘に真顔でのぞき込まれたので、豊はあわてて説明した。
「もちろん、自分で決めて辞めたんだよ。たくさんの人に喜ばれる、居心地のいいカフェをつくるんだ。そのうちパパ、人気店のオーナーになるぞ~」
「ふうん、やめさせられちゃったんじゃないなら、いいよね」
瑠華はくるりと豊に背を向けて、またテレビの前でダンスのステップの練習を始めた。
キッチンへ行くと、妻の麻衣が夕食の支度を始めているところだった。
「ちょっとだけ、ただいま」
麻衣は米を研ぐ手を休めずに、顔だけ振り返って豊を見た。
「瑠華に夢みたいなことばかり言わないでくれる?」。どうやら少し機嫌が悪そうだ。
「どうしてだよ。夢を持つって大事なことじゃないか」
「少しは現実も見てほしいのよ。来年は中学生だというのに、毎日ダンスばっかり。もっと真面目に勉強しないとついていけなくなるわ。まったく、誰に似たんだか」
豊は資金繰りの愚痴を飲み込んで、「わかったよ」と妻の肩に手を置いた。
「俺、荷物置きに来ただけだから。店に戻るよ。夕飯いらない。遅くなる」
豊は妻の返事を聞かずにそっとキッチンを出て、瑠華に手を振ると、また寒空の下、出かけていった。
夢と現実

カフェ「スマイル・ウェルカム」は、最寄りの富山駅から7分ほど歩いたところにある。
昭和初期から建つ2階建ての民家の空き物件を、風合いを生かして改修し、カフェの体裁を整えた。
豊が店に戻ると、スタッフの林拓哉がモップで床掃除をしていた。
年齢は豊の一回り下だが、なぜか昔から慕ってくれている。単発アルバイトで食いつないでいた拓哉に声をかけると、二つ返事で来てくれた。
「ただいま、拓哉。荷物届いた?」
「来ましたよ。お待ちかねの」
店の看板がようやく届いたのだ。
豊はどきどきしながら頑丈な梱包を解いた。
ケヤキの素材感を生かしたデザインだ。
「うん。いいね」
拓哉もうなずく。寡黙だが、心優しい青年だ。
「いよいよだな。よし、ポスティングするチラシの校正、仕上げてしまおう。近所の皆さんに店のオープンを知ってもらわなきゃな」
銀行残高を思い浮かべると胃がキリキリするが、えいやと気合いを入れなおした。
店舗取得費や内外装費、家具や什器や道具類の購入費などの初期費用はもちろん、1年分の家賃や人件費、仕入れ費、広告宣伝費などのランニングコストを細かく算出して、それに見合う金額を自己資金と信用金庫からの借入で用意した。
それでも、毎月の売上見込みがあってこそのシミュレーションだ。
順調に売上をつくっていけるかどうかは、ここからの自分たちの頑張りにかかっている。
豊は階段を上がって2階の奥にあるオフィスへ移動した。オフィスと言っても、2畳もないような机と椅子とパソコンだけのスペースである。
古い民家だったこの物件の裏庭には、松の木が立っていた。
表通りからは見えないが、2階に上がると、見事な枝ぶりが忽然と姿をあらわす。
窓一面に広がるこの印象的な光景に惚れ込んで、ここに決めたと言っても過言ではない。
窓の反対側の壁には、一面に家具調の本棚をしつらえた。
日本文学から海外文学、写真集や詩集、エッセイ、専門書など、本好きの豊が集めた蔵書がずらりと並べられている。
ようやく見つけた居心地のいい空間。
お客様にも、ぜひくつろいだひとときを過ごしてほしい、ゆっくり読書してほしい――それが豊の願いだった。
豊はパソコンを立ち上げ、チラシの校正を始めた。
この店は駐車場がなく、最寄り駅からも少し離れている。
まずは、徒歩圏内で来られるような近隣の人たちに、いかに愛されるかがカギを握るはずである。
長年の想いがようやく形になろうとしている。
これもひとえに、これまで出会った人々の助言や支えがあってこそだ。
感謝の気持ちを込めて、来週のオープン前夜にささやかなレセプションパーティーを開くことにしていた。
(パーティーのほうも、そろそろ準備しなくちゃな)
あれこれと用事はいっこうに減らない。今日も深夜までかかりそうだ。
レセプションパーティー

レセプションパーティーの日は、瞬く間にやってきた。
パーティーといっても、実にこぢんまりしたものだ。
1階席の各テーブルに招待客を通すと、店はにわかに活気を帯びた。
これまではただの物件だった空間が、店として息づく。
豊は感無量の思いだった。
豊と妻の麻衣はそれぞれに、各テーブルに挨拶に回る。拓哉は、ドリンクや軽食がなくならないか、目を配っている。娘の瑠華は最近お気に入りのワンピースを着て、大人の邪魔にならないよう、お行儀よく座っていた。
生命保険会社時代の仲間が3人連れだって来た。「明日のオープン、大丈夫か」「1年もつ算段はあるのかい」と、相変わらず辛口だ。
そう言いながら、多忙な彼らがこうして時間をつくって来てくれていることが嬉しかった。
限られた予算で雰囲気あふれる内外装を仕上げてくれた、施工業者さんたちも来た。
壁紙にそっと手を触れたり、建具の立てつけを見たりして、うなずきあう。
デザイナーは「最近の施工例では抜群の出来映えだよ。うちのホームページに載せていい?」とご満悦の表情だ。
彼らのプロフェッショナルな仕事ぶりに、豊は感心しっぱなしだった。
長年の友人のように盛り上がりながら施工を進めてきたのは、本当に楽しかった。
端の席で1人静かにワインを飲んでいるのは、信用金庫融資窓口の中村である。
自己資金だけでは足りそうもなく、借入先を探していたときに、偶然SNSで大学時代の文学サークルの先輩が地元の信用金庫の融資窓口にいることを見つけたのだった。
矢も楯もたまらずメールを送り、アポイントを取りつけた。
それから激しいダメ出しと経営アドバイスの末に、ようやく融資をしてくれた。
以来、先輩後輩のよしみもあってか、折に触れて様子をうかがうメールをくれていた。
「中村先輩、今日はわざわざありがとうございます」。深々とお辞儀をして、手元のグラスにワインを注いだ。
「いよいよ、明日ですね」。中村は店内を見回した。
「それにしても……」、中村はニヤっと笑ってみせる。
「立山のカフェへの思いって、大学の頃から変わっていないんだな」
豊の脳裏に、遠い過去の光景が浮かんできた。
たしかに大学の頃、カフェに関する雑文をサークルの同人誌に書いたことがあった。
あんな些細な文章を覚えてくれていたんだと思うと、豊は胸がいっぱいになった。
「ところで立山」、中村は真顔に戻り、おもむろに鞄から1枚の紙を取り出した。
「『歎異抄』、読んだことはあるかな」
「恥ずかしながら、ちゃんと読んだことはないんです。いちおう、持っているんですけど」
「そうか。これからカフェ経営を続けていくにあたって、いろいろ悩みごとも出てくると思う。『歎異抄』は心強いパートナーになるはずだよ」。そう言ってチラシを見せた。
「小杉駅の近くで、『歎異抄』の勉強会があるんだ。うちの子が通っている学習塾が会場で、そこの塾長が熱烈な『歎異抄』ファンなんだ。勉強会はすでに何年もの実績があって、参加者の評判もすこぶるいい。以前紹介した若手経営者も、視界が開けたって喜んでいたよ。よかったら、どうかな」
中村の優しさが心に沁みた。大学の頃からの想いをついに実現させた豊への、彼なりのエールなのだろう。
「じゃあこれで」と店を後にした中村の背中を見送りながら、必ず参加しようと心に決めた。
起業の不安は、こうした周りの人たちの温かい応援で、少しだけ薄まっていた。
感謝の気持ちがこみ上げ、力がみなぎってくる。
「よし」、豊はワインボトルを持ち直して、他の参加者のテーブルへ向かった。
(つづきはこちら)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから