「なぜ生きる」の答えはわずか漢字2字で答えられる~幸せと本当の幸せの違い(1)
人生の目的(なぜ生きる・生きる意味)の答えはわずか漢字2字で答えられます。目先の目標にとどまらない、自分が本当の幸せになれるヒント。
もし、「人生の目的」がなかったら、大変なことになります。
生きる意味も、頑張る力も消滅してしまうからです。
なのに、 「人生に目的なんて、ないよ」 と、言う人が、意外に多いのです。
本当にそうでしょうか。何か、大事なものを、忘れていないでしょうか。
1度きりしかない人生、後悔しないためにも、まず、「なぜ苦しくとも、生きねばならぬのか」を考えてみましょう。

「死」はいかに、人生の盲点であるか。
直面するまで、本当の怖さも、重大性も、実感できないとは、あまりにも誤算にすぎるでしょう。終幕の人生にならないと誰も気づかない落とし穴だから、かのロシアの小説家・チェーホフは、「人生は、いまいましい罠」と代表作『六号病室』で表現したのかもしれません。
かつてNHKスペシャル「世紀を越えて」の中で、「いのち」をテーマにした特集が組まれました。その一つ「遺伝子診断、新しい予知医療の光と影」に紹介された2人のアメリカ人の証言を聞いてみましょう。
「遺伝子診断」とは、遺伝子を調べ、将来、特定の病気にかかる確率を知る先端医療です。
ロサンゼルスのガン専門病院・USCガンセンターでは、遺伝子科を設け、乳ガンと卵巣ガンの遺伝子診断を始めました。遺伝子科を訪れるほとんどの人は、健康な女性です。ガンになりやすい遺伝子があるかどうかを調べ、予防に生かすためです。
ナンシー・プラウザさんは、3年前に遺伝性乳ガン、卵巣ガンの診断を受けました。48歳(当時)のナンシーさんが診断を受ける決意をしたのは、両親の病気がきっかけでした。母親は20年前、58歳で乳ガンになり、その後、すぐに亡くなっていました。父親も7年前、男性ではまれな乳ガンを発病し、遺伝性であると診断を受けたのです。
果たして乳ガンを引き起こした両親の遺伝子を、自分が引き継いでいるのか。
「ガンになるのかならないのか、ハッキリ知りたい」 という思いから、ナンシーさんは診断を受けました。
その結果、遺伝子に異常が見つかりました。70歳までに乳ガンになる可能性は、84パーセント、卵巣ガンになる可能性は27パーセントと宣告されたのです。
ナンシーさんは語ります。
「まるで何かに殴られたように感じました。とてもショックで、うろたえました。乳ガンですと言われたわけではないのに、乳ガンであることを告知されたように感じたのです」
診断から1カ月後、少しずつ落ち着いてきたナンシーさんに、医師から、予防のための方針が3つ提示されました。
1つめは、頻繁に診断を受けてガンの早期発見を目指す。
2つめは、乳ガンの予防のために開発された薬を試す。
ナンシーさんは、この2つではなく、最後に提示された方法をとる決心をしました。 それはガンになる前に、乳房と卵巣を切除するというものでした。ガンの恐怖から逃れるにはこの方法しかないと考えたのです。診断を受けてから7カ月後のことでした。
「手術を受けたくはありませんでした。つらい手術ですし、また、醜い姿になるのも嫌でした。しかし、手術を受けて、不安は、はるかに小さくなりました。毎朝、目が覚めるたびに、今日こそ、乳ガンが見つかるのでは、と恐れることもなくなりました。ですからこの決断は、私にとって最善の決断だったと思っています」
ナンシーさんは、重荷を下ろしたような笑顔で語っていました。
数年前、アメリカの人気女優、アンジェリーナ・ジョリーさん(37=当時)も、同様の決断して話題になりました。やはり遺伝子検査で、乳ガンになる確率が87パーセントと告げられたことと、56歳で母親がガンで亡くなっていたからでした。それで乳ガンになる確率が5パーセント以下に下がったといいます。
しかし、ここで考えてみたいことがあります。ナンシーさん(や私たち)が、本当に恐れているものは何なのか。それは切除手術で解決したといえるのか……。
ナンシーさんは、84パーセントの確率でガンになると宣告され、恐怖のどん底へ突き落とされました。
だが、それは「ガン」が怖かったのでしょうか。ガンが簡単に治る病気ならば、少しも恐れなかったでしょう。ガンになったら死なねばならない。死に直結するから、殴られたようなショックを受けたのではないでしょうか。発病したら死ぬ。そう思うから、毎朝、不安だったのではないでしょうか。
つまり、「ガン」が怖いと思うのは錯覚であって、本当は、その奥にある「死」が怖いのです。
ナンシーさんは、確かに、乳ガンになる可能性はなくなったかもしれません。しかし、他の病気で死ぬ可能性は少しも減っていません。乳ガンで垣間見た「死の恐怖」と、全く同じ心境を味わう日が、将来、必ず来るのですから、本質的には何も解決されていないのです。
全人類の体には、「必ず死ぬ遺伝子」が、平等に組み込まれているといってもいいでしょう。
ガンの発症率を問題にすることも大切ですが、100パーセント発症する「死」への対処が、ほとんどなされていないのは、まさに人類の盲点です。
アリゾナ州に住む、34歳(当時)のブラッド・ジェフェ氏は、遺伝子診断で、早期発症型アルツハイマーを将来発病すると宣告されました。
この病気は若くして脳細胞が萎縮(いしゅく)し始め、痴呆(ちほう)の症状を起こし、死に至る病です。発病を遅らせることも治療することもできません。
自分の強い意思で診断を望んだジェフェ氏。しかし、結果が伝えられると大きな衝撃を受けました。
「こんなことになるなんて不公平だ。人生は、何のためにあるのか」
怒りをぶちまけたあと、彼は激しく泣いたといいます。
ジェフェ氏は、毎月1回、カウンセリングを受け続けています。
ふさぎこんだ彼に、カウンセラーは、優しい声で、こう諭します。
「病気を怖がらずに、ありのままに感じるのよ」
彼は、深いため息をもらし、首を静かに振りながら答えます。
「でも、それは難しい。ありのままに感じたら変になってしまいそうだ。感じることが怖いんだ」
よく、「死」の壁の前で泣き沈んでいる人に、何の解決の道も示さず、ただ、 「ありのままに受容せよ」 と言う人があります。しかし、それは、あまりにも残酷ではないでしょうか。
「ありのままに感じたら変になってしまいそうだ」 というジェフェ氏の答えが、よく表しています。
「死」のもたらす恐怖と絶望は、直面した人でなければ理解できません。 「一生、逃れることができない遺伝子の重さ、ジェフェ氏は、その重さと向き合いながら、これからの人生を歩んでいくのです」 とNHKは番組を結んでいますが、これは1人、ジェフェ氏のことだけではないでしょう。
ジェフェ氏は「死に至る病」を、科学的に予知されただけです。私たちも、将来、必ず死にます。ただ、どんな病気で死ぬか予知できないにすぎません。
だからこそ、一生、逃れることのできない『死』の重さに向き合って、なぜ生きるのか、真剣に取り組むべきだと思います。
死の不安の影に付きまとわれている人間に、真の幸福が味わえるはずがありません。
独りで、死の恐怖におびえ、生への執着にもだえ、生きがいを見失い、最後には激しい肉体的苦痛など、全く勝ちめのない苦闘の末、何の解決も得られないまま死んでいかねばならない。こんな一大事をなぜ、人々は、真剣に考えてみようとしないのでしょうか。
「人生の目的」を論じる時に、絶対に避けて通れないのは、「私は必ず死ぬ」という事実です。
「死」は、ある日、突然、我々を襲います。
しかも、地震や台風と違って、誰一人、避けることはできません。100パーセント確実な未来です。
このことは誰でもよく知っているはずなのに、いざとなると狼狽するのは、なぜでしょうか。
「知識としての死」と、「自分の死」は、全く感じ方が違うからでしょう。
ある女性が、いつもと変わらぬ平和な日に、大腸ガンの宣告を受けた衝撃をつづっています。その一部を読んでみましょう。
次に、すぐ耳元で名を呼ばれた時、顔を上げてみて、長椅子にぎっしりと並んでいた患者達が、前の2、3列を残して、ほとんど居なくなっているのに気がついた。
壁の時計は十一時をまわっている。ここへ来て、二時間余りが過ぎたのである。
「どうも、お待たせしました」
さきほどの、若い外科医は、体をかがめると、わたしに寄り添うように、長椅子へ斜めに腰をおろした。
「これから、ちょっと検査をします。その前に、もう少しくわしく、今までの症状を聞かせてくださいませんか」
「わたしの大腸の写真に、何かあったのでしょうか」
「ええ、そうです」
まだ、三十を少し出たばかりのようにみえるその医師は、緊張した表情をしていた。
「じゃあ、痔では、なかったんですね」
「そうです」
「取らなければ、いけませんね」
「ええ、たぶん」
わたしの〈告知〉は、このようにして始まった。
そして、わたしは、この短い会話によって、その核心の部分を、正確に察知していた。ただ、それは、この瞬間には、ごく単純な〈知識〉として理解したにすぎない。
わたしは、まだ、少しも動揺してはいなかった。
医師もまた、そこへ来た目的だけを、果そうと努めていた。
「今から、もう少し、検査をします。その前に、お聞きしたいことがあります」
広いホールの中を、急ぎ足で、あるいはゆっくりと、横切っていく人がいる。
しかし、総合待合室の長椅子に座って、書類を膝に置いた白衣の医師と、患者らしい初老の女が、向かいあって話し込んでいるという光景は、ここでは別に珍しいことではない。誰も2人に注目する者はいない。

わたしは、真っすぐに医師の眼を見ていた。そして、医師もまた、少しもひるまずに、そのよく光る知的な眼で見返していた。ちょうど親と子ほどに年のひらいた医師とわたしとの間には、濃密な、親愛の気配が流れていた。
「いつごろから、出血がありましたか」
「はっきりと分かったのは、先週の木曜日に注腸検査を受けて、二日ほどしてからです」
「それまでに、何か、気がついたことがありましたか」
わたしは、その時、初めて、容易ならざる事態が、自分の体に起こっていることに気づいたのだ。
不意に、今まで立っていた足の下の地面が音もなく崩れ落ちた。
船底の腐った板を踏み抜いたような、あるいは、雪山の裂け目へひと足踏み出してしまったような空虚が、体を襲った。
わたしは、底なしの谷を落下していた。
体温が、冷えていく。こめかみが冷たい。
唇も、鼻腔も、喉もその奥の内臓まで、紙のように渇いていく。
(戻ることは、できない) と、わたしは、感じた。
(もう、助からない。もう、地上へは、もどることはできない)
絶望に打ちのめされていた。
(……しかし、なぜ、このわたしが、標的にされたのか。誰でもない、この、わたしが)
それは、無差別爆撃に似ていた。
わたしは、六十余年の今日までに、幾度も、間違った道を選んでしまった、と悔いたことはある。進学、就職、結婚、出産、夫の転勤、診療所の開設、息子の巣立ち。そんな人生の節目を、何とか辛抱を重ね、全力を尽くして切り抜けることができた。だから、六十を越えた今は、人並みの平和な家庭、穏やかな老後を迎えることができたと思っていた。これからの二十年は、いささか退屈ではあるが、もう変わりようもない日々がずっとあるばかりだと、信じ込んでいた。
その先が、目の前が、切り棄てられて見えない。何もない。つかまるものがない。助かる道がないのだ。
(磧塔ちづるさんの手記より抜粋。日本ペンクラブ編『見慣れた景色が変わるとき』収録)
この女性だけではありません。誰もが、自分自身の平均寿命までの老後を思い描いているでしょう。しかし、「死」は、情け容赦なく襲ってきます。決して、待ってはくれません。現在の生活を根底から覆す大問題なのです。
にもかかわらず、直面するまで、その一大事性が実感できないところに、人間の悲劇があります。
お釈迦様が、ある日、修行者たちに「命の長さ」をお尋ねになった。返答はまちまちであった。
「命の長さは5、6日間でございます」
「命の長さは5、6日なんてありません。まあ、食事をいたす間くらいのものでございます」
「いやいや、命の長さは一息つく間しかありません、吸った息が出なかったらそれでおしまいです」
お釈迦様は最後の答えを称賛され、
「そうだ、そなたの言うとおり、命の長さは吸った息が出るのを待たぬほどの長さでしかないのだ。命の短さがだんだんに身にしみて感じられるようになるほど、人間は人間らしい生活を営むようになるのだ」
と教えられたと、『四十二章経』に記されています。
私たちは、いつまで生きていられると思っているでしょうか。
明日、自分が死ぬとは、決して思えないでしょう。
しかも、明日になれば、また、その次の日には死なないと思います。
この繰り返しで、私たちは、いくつになっても、 「明日は死なないだろう」 と思っているのです。
この迷いを破り、真剣に「死」を見つめ、「人生の目的」達成へ向けて進まねば、本当の幸福は得られないのです。
つづきはコチラ
↓↓↓
このサイトでは、この問題について真正面から答えたメルマガと小冊子(PDF)を無料で提供しております。関心があられる方は、こちらをご覧ください。
↓↓↓
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから
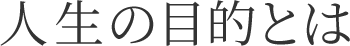
生きる意味やヒントを見つけるための特集ページです。