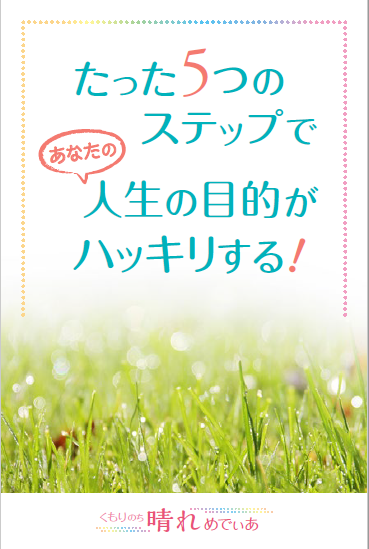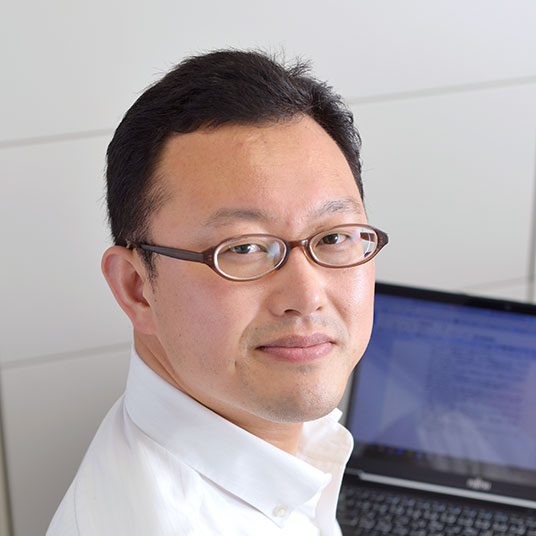
今回は、年末特集として、今話題の、2名の著者との対談を連続でお送りしています。
(前回の記事はこちらからごらんください)
1人は、レオナルド・ダ・ヴィンチの研究者である「桜川Daヴィんち」さん。ダ・ヴィンチ没後500年の今年、ルーヴル美術館をはじめ、様々な美術館でダ・ヴィンチの特別展が組まれました。そんな中、桜川さんは今年9月に『超訳 ダ・ヴィンチ・ノート』(飛鳥新社)を出版し、ラジオやネット記事などでも、最近ダ・ヴィンチと桜川さんの名前をよく見かけるようになりました。
もう1人は、アマゾン30部門で1位・人気度ランキング1位のベストセラーとなった『人生を変える 第3の幸せ』の著者、筬島正夫(おさじま・まさお)さん。「本当の幸せ」で検索1位の記事を書き、人呼んで「幸福の専門家」と言われています。
3回連続の特集、最終回は、7つのダ・ヴィンチ力の最後「幸福力」の謎に迫ってみたいと思います。
利他的じゃなければ仕事じゃない

齋藤:今日のテーマは、「幸福」についてです。
おさじま:人工知能の開発に37年取り組んできた黒川伊賀保子さんの『人間のトリセツ: 人工知能への手紙』という本の中には、「しあわせになることこそが、人類に残される最後の仕事になるかもしれませんね」と書かれています。AI時代には、「幸せ」が一つのキーワードになりそうです。
齋藤:そういえば、桜川さんも、ダ・ヴィンチ力の7つ目に「幸福力」という章を設けて、「利他的じゃなければ仕事じゃない」と書いておられますね。
桜川:はい。ダ・ヴィンチの仕事の選び方は、世の中の人に貢献する「利他」が基本でした。
例えば、14世紀のヨーロッパではペストが大流行し、人口の実に3分の1が命を落としました。
その後も伝染病の脅威が続き、危惧したダ・ヴィンチは「馬車や荷車用の通路と歩道を分けた、衛生面に配慮した空間づくり」を提案しています。
自分が今やっていることは、貢献を感じられる仕事かどうか、人を幸せにするかどうかを基準に生きた人だったのです。それが、ダ・ヴィンチを生き生きと活動させた源泉だったのだと思います。
おさじま:人を幸せにする人は、自らが幸せに恵まれるのですね。仏教にも、こんな話があります。
昔、ある所に、地獄と極楽の見学に出掛けた男がいました。最初に、地獄へ行ってみると、そこはちょうど昼食の時間でした。食卓の両側には、罪人たちが、ずらりと並んでいます。
「地獄のことだから、きっと粗末な食事に違いない」と思ってテーブルの上を見ると、なんと、豪華な料理が山盛りにならんでいます。
それなのに、罪人たちは、皆、ガリガリにやせこけている。「おかしいぞ」と思って、よく見ると、彼らの手には非常に長い箸が握られていました。恐らく1メートル以上もある長い箸でした。
罪人たちは、その長い箸を必死に動かして、ご馳走を自分の口へ入れようとするが、とても入りません。イライラして、怒りだす者もいる。それどころか、隣の人が箸でつまんだ料理を奪おうとして、醜い争いが始まったのです。
次に、男は、極楽へ向かいました。夕食の時間らしく、極楽に往生した人たちが、食卓に仲良く座っていた。もちろん、料理は山海の珍味です。
「極楽の人は、さすがに皆、ふくよかで、肌もつややかだな」と思いながら、ふと箸に目をやると、それは地獄と同じように1メートル以上もあるのです。
「いったい、地獄と極楽は、どこが違うのだろうか?」と疑問に思いながら、夕食が始まるのをじっと見ていると、その謎が解けました。
極楽の住人は、長い箸でご馳走をはさむと、「どうぞ」と言って、自分の向こう側の人に食べさせ始めたのです。
にっこりほほ笑む相手は、「ありがとうございました。今度は、お返ししますよ。あなたは、何がお好きですか」と、自分にも食べさせてくれました。男は、「なるほど、極楽へ行っている人は心掛けが違うわい」と言って感心したという話です。
同じ食事を前にしながら、一方は、俺が俺がと先を争い傷つけあっています。もう片方は、相手を思いやり、相手から思いやられ、感謝しながら、互いに食事を楽しんでいます。
どちらが幸せかということは明らかなことです。
齋藤:考えさせられる話です。利他の心掛けこそ、幸せになるために必要なことなのですね。
幸せを妨げる煩悩(ぼんのう)って?

齋藤:でも、ちょっと疑問に思うことがあるんです。利他に生きる時には、何が幸せなのかをよく知らないといけないのではないでしょうか。相手を幸せにしようと思って行動したつもりが、かえって不幸にしてしまう、ということがあるように思います。
桜川:そうですね。ダ・ヴィンチは、幸福についても様々に考察していまして、幸せを妨げるものについては、度々ノートに記しています。
例えば、手稿の中で、「人を怒らせる人間は、自分自身も破滅させる」と怒りへの戒めを記していたり、叩かれて打ち落されるクルミになぞらえて「有名になる傑作を完成させても、嫉妬のためにあの手この手で叩かれる人たちがいる」と、ねたみそねみを嘆いていたりします。
齋藤:私が読んだ中では、「低俗な人間は、食べ物が通過する袋に過ぎない」「快楽に溺れる者は、野獣の仲間になれ」のダ・ヴィンチの言葉が強烈でした。食べるのが好きな私には、ガツンとくる一節でした。
桜川:厳しい言葉ですよね。欲を満たすことなしに人間は生きていけませんし、人生の一番の楽しみは「おいしいものを食べること」という人は多い気がします。しかし「欲中心の生活を送っているのであれば、他の動物と一緒だ」と、ダ・ヴィンチは手厳しい。
おさじま:仏教では、三毒の煩悩ということが教えられています。煩悩とは、私たちを煩わせ、悩ませるもので、全部で108あると教えられています。除夜の鐘を108回つくのは、この煩悩の数から来ているのです。
中でも、私たちを特に苦しませるのが、今話題になっていた「欲」「怒り」「ねたみそねみ」の三毒の煩悩なのです。
齋藤:三毒の煩悩か。これらが幸せを妨げるのなら、なくせばいいってことですか?
おさじま:それは哲学的にいうと、「禁欲主義」ですね。多くの哲学者・思想家が諭していますが、この実践は困難なことを覚悟しなければなりません。
そもそも、仏教では”煩悩具足”といわれ、人間は欲などの煩悩でできていると教えられるのです。もし欲をなくすことが一番の幸せなら、石や屍が一番幸福ということになってしまいます。
欲や怒り、ねたみそねみがあるがままで幸せになれる

齋藤:煩悩のままに生きても破滅する。抑えることもできない。どうすればよいのでしょうか。
おさじま:その答えは「仏教」に教えられています。
世界的ベストセラーとなった『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著)にはこう書かれています。
おさじま:実は、仏教には、煩悩があるままで幸福になれる、「人間に生まれてきたのはこのためだった」といえる本当の幸せが教えられているのです。
古来、絶対の幸福を少しでも分かってもらいたいと種々に言葉を尽くし、伝え残されています。
その心の世界を一言で表した言葉の一つが【煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)】です。
欲や怒りの煩悩が「即(そく)」あるままで「菩提(ぼだい)」幸せになれる、というのが煩悩即菩提です。
つまり、煩悩を減らすのでもない、なくすのでもない、煩悩(苦しみ)が菩提(喜び)に転じる不思議な幸せなのです。
齋藤:それじゃあ、苦しみがそのまま喜びになるってことですか?苦しみがそのまま喜びに転ずるなんて、本当なのでしょうか。
おさじま:信じられないかもしれませんが、本当です。仏教には、そんな幸せが詳しく教えられていますので、ぜひ、学んでほしいと思います。
桜川:人生に対する真理を追求し続けたのがダ・ヴィンチの本質的な姿です。
仏教に教えられる本当の幸せを知ることこそ、ダ・ヴィンチの本当に知りたかったことなのかもしれませんね。
第3回のまとめ

3回にわたる年末の対談特集は、いかがでしたか?
最後に、仏教に教えられている「本当の幸せ」がハッキリ分かる、15通のメールと小冊子(PDF)を用意しました。お釈迦さまの説かれた人生の目的について、誰でも分かるような文章で、丁寧に解きほぐして解説されています。ただいま無料で配布しております。人生の目的をハッキリさせたい、と思われる方は、こちらからお受け取りください。
↓↓↓
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから