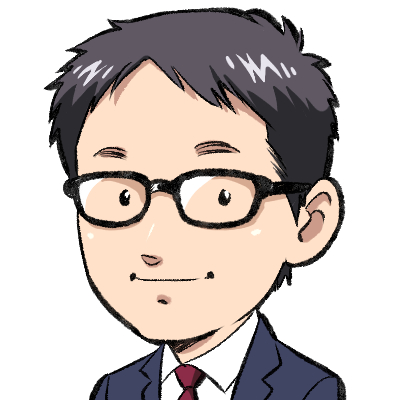
目標を打ち立てたものの、目標達成のための行動が長続きせずに、途中で挫折してしまったことはないでしょうか。
「体重を3カ月で10kg落とす!」
「TOEICで900点を取る!」
「勉強時間を1日2時間確保し、年内にこの資格を取る!」
「朝5時半に起きてジョギングし、日課にする!」
などの目標を設定し、はじめのうちはがんばるのですが、1度手を抜くと、もうどうでもよくなって、いつもの生活に戻ってしまう。
そんな自分を嫌に思い、努力すること自体をやめてしまっている方もいるかもしれません。
そのような状態に陥らずに、設定した目標をクリアし、満ち足りた気持ちになるにはどうすればいいのでしょうか。
目標達成のための手段はあふれていますが、モチベーションと目標達成の分野の第一人者が教える、科学的に効果があると実証済みの方法をご紹介します。
目標達成をあきらめている方だけでなく、目標達成に自信のある方も新たな見方を得て、ゴールへの到達率を高めることができるでしょう。
モチベーション研究の第一人者が教える、目標達成に重要な3つの要素

「どうすれば目標へ向かう行動を着実に起こせるのか」
「自分のモチベーションを上げるにはどのようにすればいいのか」
それについて明確に答えているのが、コロンビア大学の心理学博士 ハイディ・グラント・ハルバーソン氏です。
目標達成の分野の第一人者として知られ、メンタリストとして有名なDaiGoさんもハルバーソン氏の書籍を推薦書としていくつも取り上げています。
ハルバーソン氏は、目標達成に効果があるたくさんのシンプルな方法を教えています。
その目標へのアプローチ法を取り入れることで、頓挫することなく目標達成へ向かえるでしょう。
まず知っていただきたいのが、目標達成に重要とされる、以下の3つの要素です。
- マインドセット
- 行動計画
- 環境
今回は、1つ目のマインドセットについて詳しくお話ししていきます。
マインドセットとは物事への見方・考え方のことです。
目標に対してのマインドセットで特に知っていただきたいのが、次の2つです。
- 証明型
- 習得型
この2つのマインドセットとはどんなものかについて説明する前に、次のいくつかの質問に(はい、いいえ)で答えてみてください。
A2:人によい印象を与えることに強い関心がある
A3:学校や職場では、自分の能力を示すことにエネルギーを注いでいる
B1:ときには厳しい意見を言われても、率直な意見を述べてくれる友人は大切だ
B2:つねに新しい技術や知識を得ようとしている
B3:学校や職場では、つねに何かを学び、自分を成長させようとしている
Aの質問の「はい」とBの質問の「いいえ」を足した数、Aの質問の「いいえ」とBの質問の「はい」を足した数をそれぞれ出して、比較してみてください。
前者(A-はい、B-いいえ)の数のほうが多かった方は「証明型」、後者(A-いいえ、B-はい)の数のほうが多かった方は「習得型」のマインドセットの傾向があります(あくまで簡単なテストによる大まかな傾向です)。
“諸刃の剣”証明型のマインドセットの特徴と欠点

証明型のマインドセットとは、「能力を示すためによい成果を挙げること」を重視している考え方です。
- 試験でAを取る
- 売上目標を達成する
- 法科大学院に合格する
などの目に見える成果をあげて、自分の能力を証明しようとする価値観です。
ゆえに「よい印象を与えることに強い関心がある」「自分の能力を示すことにエネルギーを使っている」人は、証明型の傾向があるといえますね。
証明型の人は、「周りからの承認」=「自尊心(自分の価値)」と捉えています。
周りから認められるほど自分に価値があると思っているので、よい成果を出して周囲から評価され、自尊心を保とうとしているのです。
この証明型のマインドセットをハルバーソン氏は「諸刃の剣」と表現しています。
その理由をこう言っています。
証明型の人は、調子のいいときは高いパフォーマンスを発揮しやすいものの、いったん調子を落とし、成果を挙げられずに周りから評価されなくなると簡単に落ち込み、パフォーマンスが低調になりやすく、目標の達成そのものもあきらめやすいという傾向があるのです。
難易度が低く短期的な目標であれば、証明型のマインドセットは有利に働くのですが、長期の努力を要する目標達成には不向きなのですね。
目標達成に有利!習得型マインドセットの4つの特長

この証明型に対して、習得型のマインドセットは、「成長や進歩、技能の習得」を重視するという考え方です。
習得型の人は試験でAを取ることばかりでなく、学ぶことそのものに意識を向けていたり、売上を伸ばすことだけでなく、顧客への貢献に注目していたりするのです。
証明型の「周りからの承認」=「自尊心(自分の価値)」に対し、習得型は「自己成長(周囲への貢献)」=「自尊心」と捉えています。
優れた存在であること(= be good)ではなく、優れた存在になること(= get better)を重視しているのですね。
そのため習得型の人には、
難しい局面に直面して目に見える結果がなかなか出ないときも落ち込みにくく、モチベーションを維持しやすい(特長①)
過程を重視して、プロセスのなかに楽しみを見出だせる(特長②)
という、証明型の人にはない利点があるのです。
人に支援を求める際も、自分の代わりにまるまる何かをやってもらうという支援(便宜的な支援といいます)ではなく、やってみせてもらって、以降は自分で問題に対処するための支援(自律的な支援)を求めます。
魚釣りで例えるなら、自分の代わりに魚を釣ってもらい、魚をもらう(=便宜的支援)のではなく、魚の釣り方を教えてもらい(=自律的支援)、それ以降は自分で釣れるようにする、ということです。
自律的な支援を求める習得型の人はそれだけ成長も早くなり、成長に価値を見出してさらに目標達成へのモチベーションが高まるのですね(特長③)。
最後にもう1つの特長として、習得型の人は幸福感が得やすいのです。
ロチェスター大学の心理学教授 エドワード・デシ氏によると、人は
- 他者との深い結びつきを感じている(関係性)
- 自分には周囲に良い影響を与える能力や技術があると思っている(有能感)
- 自らの意思で動いていると感じている(自律性)
ときに、基本的な欲求が満たされて幸福感を得るといわれています。
習得型の人は自己成長、他者への貢献に価値を置いて、それを目指していることから、基本的な欲求を満たしやすいとわかりますね。
このように、習得型のマインドセットにはメリットが多く、目標達成に近づきやすいのです。
習得型のマインドセットを持つには?目標を置き換える“フレーミング”の技術

では証明型の人が習得型の人間となり、長期的な目標を達成できるようになるにはどうすればいいのでしょうか。
それには「習得型の目標」を設定することです。
勉強ならば
「〇〇点を取って、自分の能力を証明する」のではなく「この問題の意味を理解し、解けるようになる」、
仕事ならば
「これだけの営業成績を上げて、仕事ができる人間と思われる」のではなく「顧客の満足度を上げる」
など、自己成長や他者への貢献という形に目標を設定し直し、それを目指すのを楽しみにすればいいのですね。
しかし自分は習得型の目標でがんばりたいと思っても、周囲から証明型の目標を課されることはあるでしょう。
勉強なら「〇〇点を取りなさい」、仕事なら「期限までにこれだけのノルマを達成せよ」など。
そうなれば「これを達成しなければ自分はダメな人間だ」と余計なプレッシャーがかかってしまうかもしれません。
そんな証明型の目標を課せられたときに勧められているのが、「フレーミング」の技術です。
フレーミングは、考え方の「フレーム(枠組み)」を変えることで、この場合は、証明型の目標のなかに習得型の目標を設定することをいいます。
仕事でいえば「〇〇件のノルマを達成しないといけない。ノルマを達成しなければダメ人間だ」ではなく、「営業スキルを身につける機会であり、お客さんの満足度を上げるチャンスだ」と置き換えてみます。
そうすれば仮にノルマの達成が不調でも、「自分には能力がない」などのように自分を責めることなく、「お客さんの満足度は確実に上がっている。スキルも着実に身についている」と思えて落ち込みづらくなり、過程に意味と喜びを見出していけるでしょう。
勉強でいえば「ここまでの範囲は理解できた。もっと理解できるようになりたい」と考えられるのですね。
このフレーミングには絶大な効果があることが、あるビジネスマンのエピソードでわかります。
失意の底から…。フレーミングに助けられたビジネスマン

そのビジネスマンは自信家で、出世・給料・名誉など、とにかく人に勝ちたいという考えを持っていました。
ところが働き始めてしばらくして、「勝ちたいけれど勝てない。すごい人はたくさんいて、自分は人並み。自分にはそれほど才能がないってことが嫌というほどわかった」という思いを吐露したのです。
彼の自信は打ち砕かれて、プライドは傷つき、ひどく落ち込みました。
しかし彼は悲嘆に暮れることなく、発想を転換させたのです。
「とにかく勝ちたい」という目標を捨てて、「自分のチームと、お客さんが『勝つ』こと、チームのみんなと喜び、お客さんの役に立つこと」を目標にしました。
具体的には、
- 自分の他に、後輩の成果に気を配ること
- お客さんの満足度には更に気を配ること
- 上司の滞っている仕事を手伝うこと
の3つに取り組んだのです。
そうしたところ、仕事も上手くいき、チームも目立ち、憧れの先輩からは「仕事できるようになったね」と言われるようになったのでした。
「自分一人が勝ちたい。自分の力を見せつけたい」という、それまでの証明型の目標から、「チームのみんなやお客さんの役に立ちたい、喜ばせたい」という習得型の目標へフレーミングしたことで、彼自身のモチベーションも高まり、全体としても見事にうまくいったのですね。
仏教で説かれる、幸せになれるマインドセット-自利利他とは

このビジネスマンは自分中心のマインドセットから、他者中心の考え方に切り替えたことで、全体も良い方向へと進みました。
この他者を中心とした考えは、仏教の「自利利他」の精神に学ぶことができます。
利他とは他者を喜ばせること、自利とは自分の幸せということです。
他者を助けるままが、自分の喜びとなるのが自利利他ということですね。
自利利他とは反対に、自分さえよければいいと思い、自分の利益のみを優先させる心は「我利我利」といわれます。
我利我利の心では、一時的にはうまくいったように思えても、やがては周囲から疎まれ、行き詰まり、孤独になってしまいます。
仏教では我利我利は嫌われ、その反対の「自利利他」の精神こそが勧められているのです。
目標達成のマインドセットの観点からも、他者を中心に置く自利利他の精神は、習得型のマインドセットとも重なるところがあると思います。
なかなか目標達成に進めずに、落ち込みそうなときこそ、周囲への貢献に目を向けてみてください。
きっと新たな素晴らしい視点が得られて、目標達成への意欲がグンと高まるでしょう。
このような、心理学と仏教の視点から、役立つ内容を、ワークショップを開催してお伝えしております。東京近辺にお住まいの方は、ぜひ、下のボタンをクリックしてご参加ください。
↓↓↓
(参考文献)
『やってのける~意志力を使わずに自分を動かす~』(ハイディ・グラント・ハルバーソン著 大和書房)
『「仕事ができるやつ」になる最短の道』(安達裕哉著 日本実業出版社)
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


