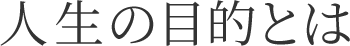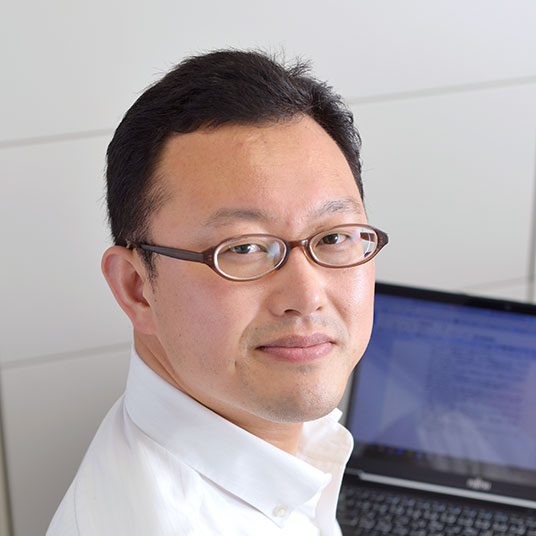
山高帽にチョビヒゲ、ドタ靴にステッキ――。
こんなトレードマークで一世を風靡したのが、喜劇王チャールズ・チャップリン(1889-1977)です。
俳優、映画監督として知られ、『キッド』『黄金郷時代』『街の灯(ひ)』『モダン・タイムス』『独裁者』『殺人狂時代』『ライムライト』など、世界中に愛される作品を数多く送り出しました。
誰でも一度は、思わず笑いに誘う彼の姿を目にしたことがあるでしょう。
そのコミカルな動きには、当時の観客たちも抱腹絶倒でした。
皆があまりにも激しく笑い転げるので、映画館で2週間も上映すると客席のボルトが緩んでしまい、定期的に固く締め直さなければならなかった、というエピソードが残るほどです。
しかも、チャップリンのすごいのは、単なる喜劇では終わらせないところでした。
見飽きることのない作品の魅力は、どこから生まれたのでしょうか。
人生は苦しみの連続

チャップリンは、芸人の両親のもとロンドンに生まれましたが、1歳の時に両親が離婚してしまいます。
酒に溺れがちだった父親と離れ、幼い彼は、4歳年上の義兄と、母の元で暮らすことになりました。
父親からの仕送りは滞りがちでした。
喉を痛めて舞台を去った母親は、針仕事で家計を支えるものの、一家は文字通り、食うや食わずの極貧生活が続きます。
服を買う金がないので、いつも着るのは擦り切れた服、靴がないので母親の靴を履き、貧民スープ接待所へ通っては、その日1回きりの食事を持ち帰るという有様でした。
あまりの窮乏に、とうとう、母親は精神を病んでしまいます。
こんな体験からにじみ出た言葉だったのでしょう。
『自伝』に彼は、「賢者だろうと愚者だろうと、人間みんな苦しんで生きるよりほかないのだ」*1と記しています。
人生は苦しみの連続ということを、身にしみて感じていたようです。
映画に込めた人生の不条理

24歳でハリウッド・デビューを果たしたチャップリンは、夢中で映画を作り続けました。
彼の映画で笑いとともに描かれるのは、人間が露呈する、どうしようもない愚かさや矛盾、不条理な真実です。
それぞれの作品に、チャップリンならではの鋭い視点が光っています。
例えば、現代の大量生産システムを風刺した彼の代表作、『モダン・タイムス』を見れば、歯車の世界でもがく主人公は、どう生きるかに振り回されて人として大切なことを見失っている、私たちのことだと気づかされるでしょう。
また、『独裁者』では、多くのユダヤ人を抹殺したヒトラーをコメディタッチで批判しながら、絶対的な権力を手にして本性むき出しになった人間が、いかに危険な存在になり得るかを描こうとしました。
最後の6分間の演説シーンは、特に有名です。
この演説に対してはスタッフからも反対の声が強く、営業担当からは「この演説で売り上げが100万ドル減るからやめてくれ」と抗議を受けます。
しかし、チャップリンは「500万ドル減ってもやる」と言って撮影を断行しました。
ブラックユーモアに満ちた『殺人狂時代』では、死刑を宣告された主人公に、「1人を殺せば悪党だが、百万人を殺せば英雄だ」*2のセリフを言わせ、人間の勝手に決めた罪悪の矛盾を浮き彫りにしています。
苦悩のときは、哲学か、ユーモアか

彼にとって笑いとは、そんな私たちが、苦しい人生を生きていくのに不可欠なものでした。
苦しい人生、なぜ生きるのか。
ユーモアの中にも、常に、生きる意味という人間不変のテーマを問うたからこそ、チャップリンの作品は、色あせないのではないでしょうか。
[出典]
*1 チャールズ・チャップリン(著)『チャップリン自伝』 新潮社
*2 清原伸一(編)『週刊100人 歴史は彼らによって作られた チャールズ・チャップリン』 ディアゴスティーニ・ジャパン
*3 チャールズ・チャップリン(著)『チャップリン自伝』 新潮社
こちらも、よかったらごらんください。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから