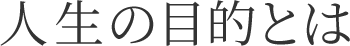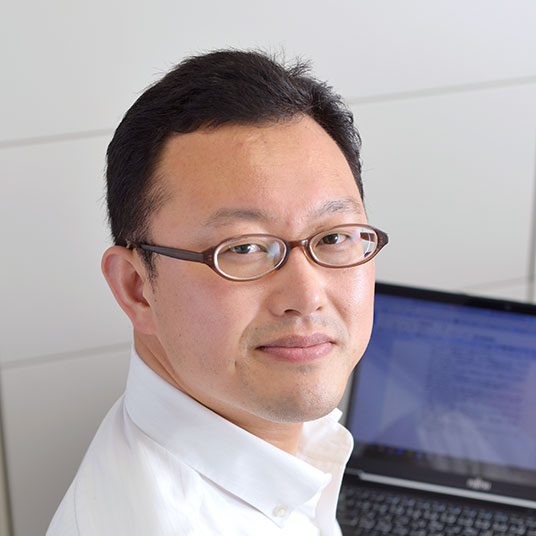
お札の肖像画や、教科書で有名な偉人が、明治の文豪・夏目漱石です。
整えられた髭の奥にある瞳は、どこか遠くを見つめているようで、その心の内までは読み取れません。
『吾輩は猫である』『坊っちゃん』など、ユーモア溢れる作品のイメージが強い漱石ですが、実はその生涯が、壮絶な「苦しみ」との戦いであったことをご存じでしょうか。
「人間は生きて苦しむ為めの動物かも知れない」
これは、漱石がロンドン留学中に妻へ送った手紙の一節です。
人生の折り返し地点を過ぎ、家庭や仕事、そして自分自身の生き方にふと迷いを感じることのある私たち40代にとって、漱石の抱えた葛藤は、驚くほど生々しく響きます。
文豪・夏目漱石は、なぜこれほどまでに苦しみ、そしてその苦しみの果てに何を見ようとしたのでしょうか。
「何をしていいか分からない」26歳の焦燥

夏目漱石、本名・金之助が生まれたのは、慶応3年(1867年)。まさに江戸が終わり、明治が始まろうとする激動の時代でした。
しかし、彼の生誕は決して家族から祝福されたものではありませんでした。
夏目家は名主を務める家柄でしたが、金之助が生まれた時、母はすでに高齢(当時としては晩産の40歳過ぎ)で、生活にも余裕がありませんでした。
「恥かきっ子」「厄介者」として扱われた金之助は、生まれてすぐに古道具屋の店先に里子に出されてしまいます。
姉が不憫に思い連れ戻したものの、すぐにまた別の家(塩原家)へ養子に出されます。
幼い金之助にとって、「自分はこの世に必要とされていないのではないか」という不安は、原風景として心に刻み込まれたことでしょう。
その後、養父母の不和により9歳で実家に戻りますが、実の父は彼を「金之助」とは呼ばず、「おい」と呼んで冷遇しました。
幼少期に十分な愛情を受けられなかった孤独。これが、漱石の生涯につきまとう「不安」の根源だったのかもしれません。
頭脳明晰だった漱石は、猛勉強の末、現在の東京大学英文科に入学します。
エリートコースを歩み始めた彼ですが、心は満たされませんでした。
大学卒業後、26歳で教師になりますが、「これは自分の本領ではない」という違和感が常にありました。
後に彼は講演『私の個人主義』で、当時の心境をこう語っています。
〈私はこの世に生れた以上何かしなければならん、といって何をして好いか少しも見当が付かない〉
「何かしなければならない」という焦燥感と、「何をすればいいかわからない」という虚無感。
これは現代を生きる私たちも、ふとした瞬間に感じるものではないでしょうか。
29歳で鏡子夫人と結婚。しかしその4年後、文部省の命により、英語研究のため単身イギリスへ留学することになります。
これが、漱石にとって最大の試練の始まりでした。
ロンドンの霧の中で見失った「私」

1900年、ロンドンに渡った漱石を待っていたのは、輝かしい洋行生活ではなく、どん底の孤独でした。
当時のロンドンは世界一の大都市。しかし、東洋人である漱石は、街を歩けばジロジロと見られ、身長の低さや容姿の劣等感に苛まれます。
さらに深刻だったのは、経済的な困窮です。国からの留学費は乏しく、物価の高いロンドンでは生活するだけで精一杯。研究書を買う余裕もありません。
「英文学」という巨大な山を前に、日本人である自分がそれを研究する意味を見失い、漱石は極度の神経衰弱(ノイローゼ)に陥ってしまいます。
下宿に引きこもり、誰とも口を利かず、ただ涙を流す日々。
現地の日本人仲間からは「夏目が発狂した」という噂さえ立ちました。
この最も辛い時期に、妻・鏡子へ送った手紙に記されたのが、冒頭の言葉です。
〈人間は生きて苦しむ為めの動物かも知れない〉
この言葉は、単なる愚痴ではありません。
「苦しみこそが人間の本質であり、そこから逃れることはできない」という、絶望に近い苦しみを直視しようとする、漱石の悲痛な叫びでもありました。
エリートの転落と、人生を変えた「猫」

失意のうちに帰国した漱石を待っていたのは、安息ではなく、さらなる現実の重圧でした。
彼が留学している間、留守宅を預かっていた親戚が失職。妻や子供たちは、漱石の古い着物を縫い直して着るほどの極貧生活を送っていました。
エリートであるはずの帝大講師の職に就いても、給料は安く、生活費を稼ぐために他の学校の講師も掛け持ちする日々。教壇に立ち、疲れ果てて帰宅し、研究などできるはずもありません。
さらに追い打ちをかけたのが、親族たちです。
「洋行帰りなら金があるはずだ」
そう思い込んだ兄や、かつて縁を切ったはずの養父が、入れ替わり立ち替わり金の無心にやってくるのです。
愛情を与えてくれなかった親族が、金だけを求めて群がってくる。漱石の人間不信は極限に達しました。
家では些細なことで激昂し、妻や子供に当たり散らす日々。いわゆるDVに近い状態だったとも言われています。
しかし、妻の鏡子だけは、そんな夫を見捨てませんでした。「夫は病気なのだ」と腹を括り、猛獣使いのように漱石を支え続けたのです。
「不愉快だから、どうかして好い心持ちになりたい」
そう漏らす漱石に、友人の高浜虚子が勧めたのが「小説を書くこと」でした。
気晴らしのつもりで書いたのが、あの『吾輩は猫である』です。
37歳にして初めて書いたこの小説が、爆発的な人気を博します。
鬱屈した思いを猫の視点を借りて笑い飛ばすことで、漱石は初めて「生きる手応え」をつかんだのです。
書けば書くほど、苦しみは深くなる

小説家として生きる覚悟を決めた漱石は、40歳で教職を辞し、朝日新聞社に入社します。
安定した職を捨てての転職は、当時としては異例の決断でした。
連載小説『虞美人草』が予告されると、三越呉服店が「虞美人草浴衣」を売り出し、街中で新聞販売員が「漱石のぐびじんそ~う!」と叫ぶほどの社会現象となります。
『三四郎』『それから』と次々に傑作を世に送り出し、漱石は一躍、時代の寵児となりました。
しかし、作家としての成功が、彼の苦悩を消し去ることはありませんでした。
むしろ、「書けば書くほど、苦しみは深くなる」――それが漱石の実感だったようです。
子沢山(最終的に2男5女)の生活は相変わらず苦しく、随筆『思い出す事など』には、こう記されています。
〈自活の計に追われる動物として、生を営む一点から見た人間は、まさにこの相撲のごとく苦しいものである〉
生きるために働く。働くために生きる。その終わりのないサイクルの虚しさ。
そして、本当の地獄は、自分の内面にありました。
45歳で書いた『行人(こうじん)』には、主人公の兄・一郎の言葉として、漱石自身の悲鳴のような独白が描かれています。
兄さんは落ち付いて寐ていられないから起きると云います。起きると、ただ起きていられないから歩くと云います。歩くとただ歩いていられないから走ると云います。既に走け出した以上、何処まで行っても止まれないと云います〉
立ち止まることが許されない。死ぬまで走り続けなければならない。
これは、現代の競争社会に生きる私たちが感じる閉塞感と、恐ろしいほど重なります。
創作活動さえも、生きる目的にはなり得ない。書くことは救いではなく、新たな苦しみの「手段」に過ぎないのではないか。そんな虚無感が漱石を蝕んでいきました。
「則天去私」になれなかった

明治43年(1910年)、43歳の時に漱石を大きな転機が襲います。
胃潰瘍の療養のために訪れた伊豆の修善寺で、大量に吐血し、30分近く人事不省に陥ったのです。
奇跡的に一命を取り留めた漱石は、死の淵を見たことで、心境に変化が表れます。
「自分は生かされている」という感覚。
これが、晩年の彼の思想とされる「則天去私(そくてんきょし)」――小さな私心を捨て、天の理(自然の法則)に従って生きる――へと繋がっていきます。
しかし、悟りを開いて穏やかになったかといえば、そうではありませんでした。
現実の生活では、最愛の五女・ひな子の急死という悲劇に見舞われます。
敬愛していた親鸞聖人の教えに救いを求めようとしましたが、ひな子の通夜で僧侶が見せた強欲で下品な態度に失望し、宗教的な救済さえも信じられなくなってしまいます。
「則天去私」という理想を掲げながらも、現実には嫉妬や執着、人間関係の軋轢に苦しみ続ける。
晩年、ある禅僧へ送った手紙には、素直な心の内が綴られています。
〈私は五十になってはじめて道に志す事に気のついた愚物です。その道がいつ手に入るだろうと考えると、大変な距離があるように思われてびっくりしています〉
自分は悟りなど開いていない。理想と現実の距離に愕然としているただの「愚物」だ。
そう認めざるを得ない弱さこそが、漱石の真実の姿だったのです。
「それでも生きたい」――最期の言葉が教えるもの

大正5年(1916年)、12月。友人の結婚披露宴に出席し、無理をして脂っこい料理を食べた翌日、漱石は倒れました。持病の胃潰瘍が悪化したのです。
死の床についた漱石。いよいよ臨終の時が迫ったその瞬間、彼は寝間着の胸をはだけて叫びました。
「ここに水をかけてくれ! 死ぬと困るから……」
これが、文豪の最期の言葉でした。意識を失い、そのまま49年の生涯を閉じました。執筆中だった長編『明暗』は、未完のまま遺されました。
「死ぬと困る」。
生きることは苦しい。人間は苦しむために生まれた動物かもしれない。そう嘆き、苦しみ続けた漱石が、最後の最後に発した言葉は、生への強烈な執着でした。
どんな教養を身に着け、心を鍛錬し、信念を固めていても、臨終の嵐の前には、ひとたまりもない。人生の最大事に直面した漱石の、痛烈な叫びでしょう。
果たして、真の平安はどこにあるのでしょうか。
人生の苦海を渡す「大船」

夏目漱石の人生を見ても、人生は苦しみの連続です。
仏教では、苦しみの連続の人生を、荒波の絶えぬ海に例えて「難度の海」と教えられています。
一つ乗り越えて、やれやれと一息つく間もなく、すぐ次の波がやってきます。
家庭や職場での面倒な人間関係、子育ての不安、病や老いとの闘い、家族の介護、借金の重荷、交通事故、地震、台風、火事など、次々と「苦難」「困難」「災難」の波に、襲われます。
どんなに必死に泳いでも泳いでも、その先には水平線のほか、何も見えない。
たどり着くべき何ものも見えず、最後、土左衛門になるのなら、人は、何のために生きるのでしょうか。
鎌倉時代の古典『教行信証』には、次のように記されています。
生きていくだけで精一杯の、苦しい人生(難度の海)を、明るく楽しく渡してくれる大きな船があります。
仏教には、その苦しみの海を楽しく渡す、大きな船があるぞ。早く乗せていただきなさいと教えられています。それが「人は、なぜ生きるのか」の答えなのだと明示されているのです。
生きる目的がハッキリすれば、病気がつらくても、人間関係に落ち込んでも、競争に敗れても、「大目的を果たすため、乗り越えなければ!」と〝生きる力〟が湧いてきます。
なぜ生きるのか、もっと詳しく知りたい人は、こちらをごらんください。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから