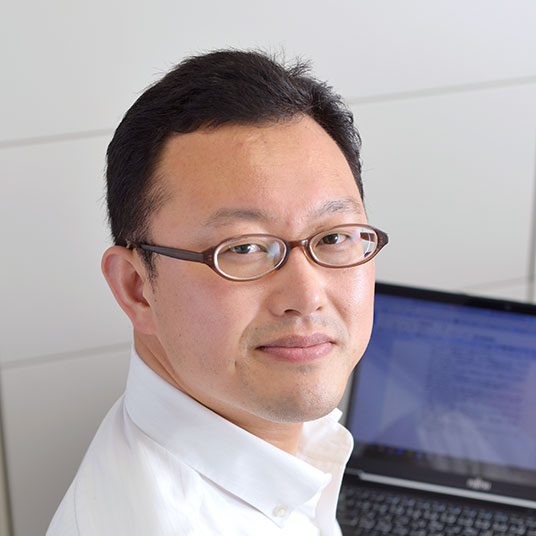
皆さんは、「ホンダ」という名前にどんなイメージをお持ちでしょうか?
世界的な自動車メーカー、F1レースでの活躍、あるいは街を走るスーパーカブ……。
私たちの生活に身近な存在である世界のHONDAですが、その始まりが、静岡県の小さな町工場だったことをご存じの方は多いかもしれません。
創業者である本田宗一郎。「オヤジさん」と親しみを込めて呼ばれた彼は、あふれんばかりの情熱と、人間味そのもののような人でした。
創業間もない頃、彼は工場の庭にあったみかん箱の上に立ち、従業員たちに向かってこう叫んでいたといいます。
「俺たちは、ここから世界一になるんだ!」
当時、まだ浜松の小さな工場に過ぎなかった頃の話です。
周囲からは「ホラ吹き」と笑われたかもしれません。
けれど、彼だけは本気でした。その瞳には、まだ見ぬ未来がはっきりと映っていたのです。
私たちが生きる現代も、先が見えない不安や、変化への戸惑いでいっぱいです。
ふと「自分の人生、このままでいいのかな」と立ち止まる瞬間があるのではないでしょうか。
そんな時、本田宗一郎の言葉と生き方は、凝り固まった私たちの心を優しく、そして力強く解きほぐしてくれます。
絶望の淵で選んだ「世界への挑戦状」

本田宗一郎の道のりは、決して順風満帆なサクセスストーリーではありませんでした。
むしろ、何度も壁にぶつかり、そのたびに泥臭く這い上がってきた歴史といっても過言ではありません。
戦後、焼け野原の中で彼が最初に着目したのは、旧陸軍が放出した通信機用の小型エンジンでした。
それを自転車に取り付けた、通称「バタバタ」。
「買い物に行く妻の自転車を楽にしてやりたい」
そんな優しさから生まれたとも言われるこの発明は、人々の足として大ヒットし、ホンダの基礎を築きました。
しかし、彼の夢はそこで終わりません。
「世界水準の製品を作りたい」。その一心で、当時の資本金の75倍にもあたる4億5千万円もの巨額を投じ、海外から高性能な工作機械を輸入するという、常識外れの「賭け」に出ます。
「良い機械がなければ、良いものは作れない」
その信念は本物でしたが、現実は過酷でした。
折からの不況に加え、主力商品だったスクーター「ジュノオ号」の失敗や、エンジンの不具合によるクレームの嵐……。
いわゆる「五重苦」が会社を襲い、ホンダは倒産寸前の危機に立たされます。
普通なら、守りに入り、縮こまってしまう場面です。
しかし、本田宗一郎は違いました。
なんとこの最悪のタイミングで、世界最高峰のバイクレース「マン島TTレース」への出場を宣言したのです。
社員たちは耳を疑いました。明日の給料さえ危うい時に、世界レース?
しかし、彼は言いました。
「何が何でも出る。今みんなが苦労してる時だろ。こんな時こそ夢が欲しいじゃないか」
苦しい時だからこそ、足元を見るのではなく、遥か遠くの星を見上げる。
それは、絶望に沈みかけていた社員たちの心を鼓舞し、一つにするための、彼なりの愛情とリーダーシップだったのです。
「やってやるぞ!」
その宣言を合図に、若い技術者たちは工場に泊まり込み、油まみれになって開発に没頭しました。
そして宣言から7年後の1961年、ホンダはついにマン島TTレースで優勝。しかも、1位から5位までを独占するという快挙を成し遂げ、世界中を驚嘆させたのです。
「120%の良品」に込められた、たった一人の誰かへの想い

本田宗一郎を語る上で欠かせないのが、彼の口癖だった「やってみもせんで、何がわかる」という言葉です。
新しいことに挑戦すれば、失敗はつきもの。彼は常識にとらわれない発想を愛し、失敗を恐れずに挑む姿勢を誰よりも大切にしました。
「木登り以外に取り柄のない猿が、木から落ちてはいけない。しかし、新しい木登り技術を学ぶために落ちるなら、それは尊い経験だ」
そんなふうに、前向きな失敗(=試み)を「尊い」とさえ表現して奨励したのです。
しかし、本田宗一郎はただの「イケイケドンドン」な経営者ではありませんでした。
彼の中には、挑戦者としての顔と同時に、お客様を想う繊細で厳格な「商売人」としての顔がありました。
ある時、品質管理の担当者が「千台に一台くらいの不良品は仕方がない」と言い訳をしたことがあります。
それを聞いた宗一郎は、烈火のごとく怒りました。
「ふざけるな! お前たちにとっては千台に一台かもしれないが、なけなしのお金でそれを買ってくれたお客様にとっては、それがすべてなんだ。100%の不良品なんだぞ!」
そして、こう続けました。
「だから俺は、『120%の良品』を目指せと言うんだ」
人間がやることだから、100%を目指してもミスが出るかもしれない。だからこそ、最初から120%を目指してようやく、お客様に100%の満足を届けられるのだ、と。
世界最高峰のレースで培った技術を、そのまま大衆車である「スーパーカブ」に惜しみなく注ぎ込んだのも、この哲学があればこそでした。
レースという極限状態で磨かれた「壊れないエンジン」の技術は、そば屋の出前や新聞配達、そして毎日の買い物に使う人々の「日常の足」を支えるためにこそ、必要だと考えたのです。
世界一の技術を、ふつうの人々の暮らしのために。その根底にあったのは、技術への過信ではなく、製品を使ってくれる「たった一人の誰か」への、深く温かい誠実さでした。
人生というレースを走る私たちへ

私たちは、経験を重ねた分だけ、「これをやったらどうなるか」となんとなく予測がつくようになり、傷つくことを恐れて、新しい一歩を踏み出すのを躊躇してしまうことがあります。
「いい歳をして失敗したら恥ずかしい」
「今さら新しいことなんて」
そんな心の声が聞こえてくることもあります。
しかし、未来のために、より良くあろうとするために転ぶことは、決して恥ずかしいことではなく、「尊い経験」であり、その傷跡さえも勲章なのだということを、本田宗一郎は教えてくれます。
スーパーカブが世界中で愛されたように、私たちが日々の生活の中で、家族のために、仕事のために、誰かのためにと懸命に積み重ねている「試行錯誤」は、きっと誰かの笑顔につながっています。
完璧じゃなくてもいい。失敗してもいい。
大切なのは、目の前のことに誠実に向き合い、「ちょっとやってみようか」と心を躍らせるその一歩です。
もし今、何かに迷っているなら、心の中のリトル・宗一郎に問いかけてみてください。
「やってみもせんで、何がわかる?」
きっと、背中をバンと叩いて、笑顔で送り出してくれるはずです。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


