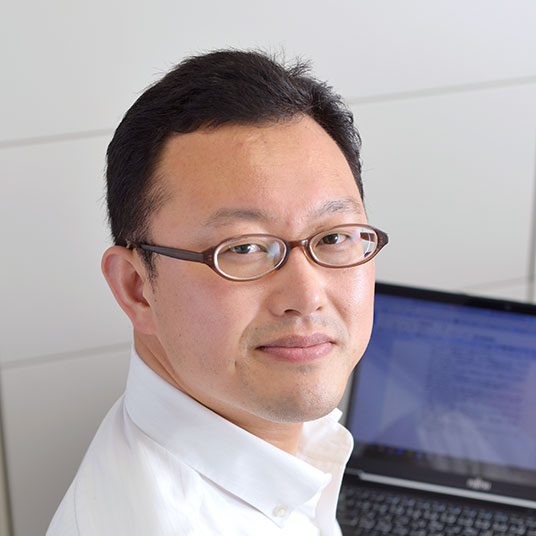
現代社会を生きる中で、漠然とした息苦しさや憤りを感じることはないでしょうか。
そんな感覚に陥っているのは、あなただけではないかもしれません。
2025年6月29日の『日本経済新聞』に、「『怒っている人』世界で増加中」という見出しが躍りました。
社会や政治に対して憤りを感じる人の割合が、世界中で増加傾向にあるといいます。
米国の調査会社ギャラップが約140の国と地域で実施した調査では、「昨日、『怒り』の感情を持つことが多かった」と答えた人の割合が、2014年の世界平均18%から、2023年には22%にまで上昇しました。
わずか9年間で、実に2割以上も「怒っている人」が増えた計算になります。
特に、新型コロナウイルスのパンデミックが世界を覆った2020年には、その割合は24%に達しました。
その後も高水準で推移しており、私たちの社会が、見えない「怒り」という感情に覆われている現実を浮き彫りにしています。
では、なぜこれほどまでに、世界は怒りに満ちてしまったのでしょうか。
そして、私たちのこの心を、どうすれば解決できるのでしょうか。
SNS時代が加速させる「比較地獄」

怒りの源泉を探る第一歩として、まず「幸福」そのものの性質について考えてみましょう。
私たちは、何を基準に「自分は幸せだ」と感じるのでしょうか。
多くの学術論文や研究が指摘しているのは、人間の幸福感が「相対的」であるという事実です。
例えば、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらが提唱した「プロスペクト理論」では、人は、基準となる何かからの「変化」や「差」に強く影響を受けるとされています。
給与の額そのものよりも、「去年より昇給した」という事実の方が、大きな満足感をもたらすのです。
また、米国の心理学者レオン・フェスティンガーによる「社会比較理論」も、この点を裏付けています。
この理論によれば、人は自分の能力や意見、そして幸福感を、他者と比較することによって評価する傾向があります。
特に、自分と境遇が似ている友人や同僚、同年代の他者との比較は、私たちの幸福度に大きな影響を与えます。
親しい友人が昇進したり、大きな成功を収めたりすると、自分の状況が何も変わっていなくても、なぜか心がざわつき、満足度が下がってしまう経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
この「他人と比べてしまう」という人間の性質は、かつてはごく身近なコミュニティの中で完結していました。
しかし、SNSが生活の隅々にまで浸透した現代において、この比較のメカニズムは、私たちをかつてないほどの不幸へと駆り立てています。
InstagramやX(旧Twitter)のタイムラインを眺めれば、そこには友人や著名人の「最も輝いている瞬間」が切り取られ、あふれています。
豪華な海外旅行、高級レストランでの食事、仕事での成功、幸せそうな家族写真。
それらは、彼らの日常のほんの一部分に過ぎないにもかかわらず、私たちの目には、まるで他人の人生が常にきらびやかな出来事で満ちているかのように映ります。
仮に、友人が100人いて、それぞれが年に一度だけ特別な体験をSNSに投稿したとしましょう。
すると、自分のタイムラインには、計算上3〜4日に一度は誰かの「特別な日」が流れてくることになります。
その結果、「自分はこんなに平凡な毎日を送っているのに、周りの人たちはなんて充実しているのだろう」という劣等感を抱いてしまうのです。
アルゴリズムは、私たちの関心を引く刺激的な投稿を優先的に表示するため、この傾向はさらに加速します。
私たちは、無意識のうちに24時間365日、世界中の人々の「最高の瞬間」と自分自身の「平凡な日常」を比較し続けるという、終わりのない競争に参加させられています。
この絶え間ない比較こそが、現代社会に蔓延する不満や嫉妬、そして「怒り」の大きな原因の一つなのです。
幸福が相対的なものである以上、他者との比較ゲームから降りない限り、心の安らぎを得ることは極めて困難であると言えるでしょう。
不安が生み出す「陰謀論」という名の怪物
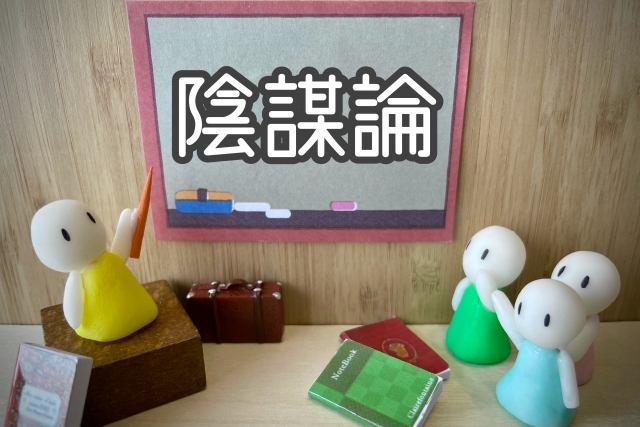
さらに、社会全体に広がる「ぼんやりとした不安」は、より危険な現象へと人々を駆り立てます。
それが「陰謀論」です。
ジャーナリストの松浦晋也氏は、日経ビジネスのコラムの中で、ワクチンを巡る言説を例に、人が陰謀論に囚われるメカニズムを鋭く分析しています。
なぜ、近代医学が多大な恩恵をもたらしてきたワクチンに対して、「実は毒である」「人口を削減するための陰謀だ」といった非科学的な言説がなくならないのでしょうか。
松浦氏によれば、陰謀論は「自分には理解できない恐怖」を、「自分に理解できる恐怖に置き換える」機能を持っているといいます。
「自分の体によく分からないものを入れるのは怖い」という漠然とした不安に対し、「その正体は毒だ」という単純明快なレッテルを貼る。
そして、「なぜ毒を広めるのか」という問いに対し、「世界を裏で操るディープステートや、特定の勢力が利益を得るためだ」というストーリーを与える。
そうすることで、得体の知れない不安は、「特定の敵」という分かりやすい形と名前を得て、人は一時的な“安心”を手に入れるのです。
この構造は、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という言葉で説明できます。
暗闇で揺れる枯れススキが、なぜ怖いのか。それは、その正体が分からないからです。
しかし、それに「幽霊」という名前と形を与えると、「ああ、あれは幽霊か」と、未知の不安は既知の恐怖へと変わり、ある種の納得感が生まれます。
しかし、陰謀論と幽霊には決定的な違いがあります。
それは、「憎悪と社会の分断を生むか否か」です。
幽霊の場合、「幽霊なら仕方ない」と、恐怖を受け入れ、共存しようという気持ちにつながることがあります。
それは、不確かな世界を生き抜くための、ある種の知恵とも言えるかもしれません。
一方で、陰謀論は必ず「あいつらが悪い」という他者への攻撃に行き着きます。
「ワクチンで儲けている製薬会社を許すな」「社会を混乱させる〇〇人を排斥しろ」といった形で、憎悪を煽り、社会に深刻な亀裂を生み出すのです。
この陰謀論に惹きつけられるのは、決して一部の特殊な人々ではありません。
松浦氏が指摘するように、むしろ今の自分の環境に強い不安を感じている、ごく普通の人々です。
作家・芥川龍之介は、「何か僕の将来に対する唯ぼんやりとした不安」と動機を綴り、35歳で服毒自殺しました。
この感覚を抱えながら、どうにかしてその不安を解消したいと願う人々が、陰謀論という偽りの希望に引き寄せられていきます。
「自分は真面目に生きているのに、なぜ報われないのか」「どうしてこんなに生きづらいのか」という切実な問いに対し、陰謀論は「あいつらが悪いからだ」という、抗いがたいほど魅力的な答えを与えてくれます。
それを信じた人は、「自分だけが世界の真実に気づいた」という優越感に浸り、その「真実」を広めることに倒錯した正義感すら抱くようになります。
近年、世界中で見られる「自国第一主義」の台頭も、この文脈で捉えることができます。
しかし、歴史が証明しているように、特定の集団を排除することで成り立つ幸福は存在しません。
ナチス・ドイツが「ユダヤ人が悪い」という陰謀論の果てに何をもたらしたかを、私たちは知っています。
誰かを悪者に仕立て上げ、社会から排除しようとする試みは、巡り巡って自分自身が「非国民」「敵」として認定される恐怖の社会へとつながります。
それは、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』で、自分だけが助かろうと糸に群がる亡者たちを蹴落としたカンダタの頭上で、糸がぷつりと切れてしまった光景を思い起こさせます。
分断の先に待っているのは、全員の不幸と社会の崩壊だけなのです。
苦悩の根元「無明の闇」

ここまで、現代社会に蔓延する「怒り」が、SNSによる「相対比較」と、社会への「ぼんやりとした不安」に根差していることを見てきました。
他者と比べては落ち込み、見えない不安から逃れるために分かりやすい敵を作り出して攻撃する。この、さらに奥深くには、一体何があるのでしょうか。
仏教では、私たちのあらゆる苦悩の根本原因を「無明の闇(むみょうのやみ)」という一言で喝破します。これは「人生の目的が分からず、生命の歓喜が感じられない心」を指します。
何のために生まれ、どこへ向かって生きていくのか。そして、死ねばどうなるのか。この人生の根本的な問いに対する答えが見出せず、確かな生きる目的が分からないまま、暗闇の中を手探りで歩むような心。
これこそが、尽きることのない不安や焦燥といった、人間のあらゆる苦悩を生み出す根源であると、仏教は古来より説いてきたのです。
芥川が感じた「唯ぼんやりとした不安」もまた、この「無明の闇」の深淵を覗き込んだ者の、魂の戦慄であったのかもしれません。
私たちはこの闇の中で苦しみ続けるしかないのでしょうか。
『歎異抄』に学ぶ真の安らぎ
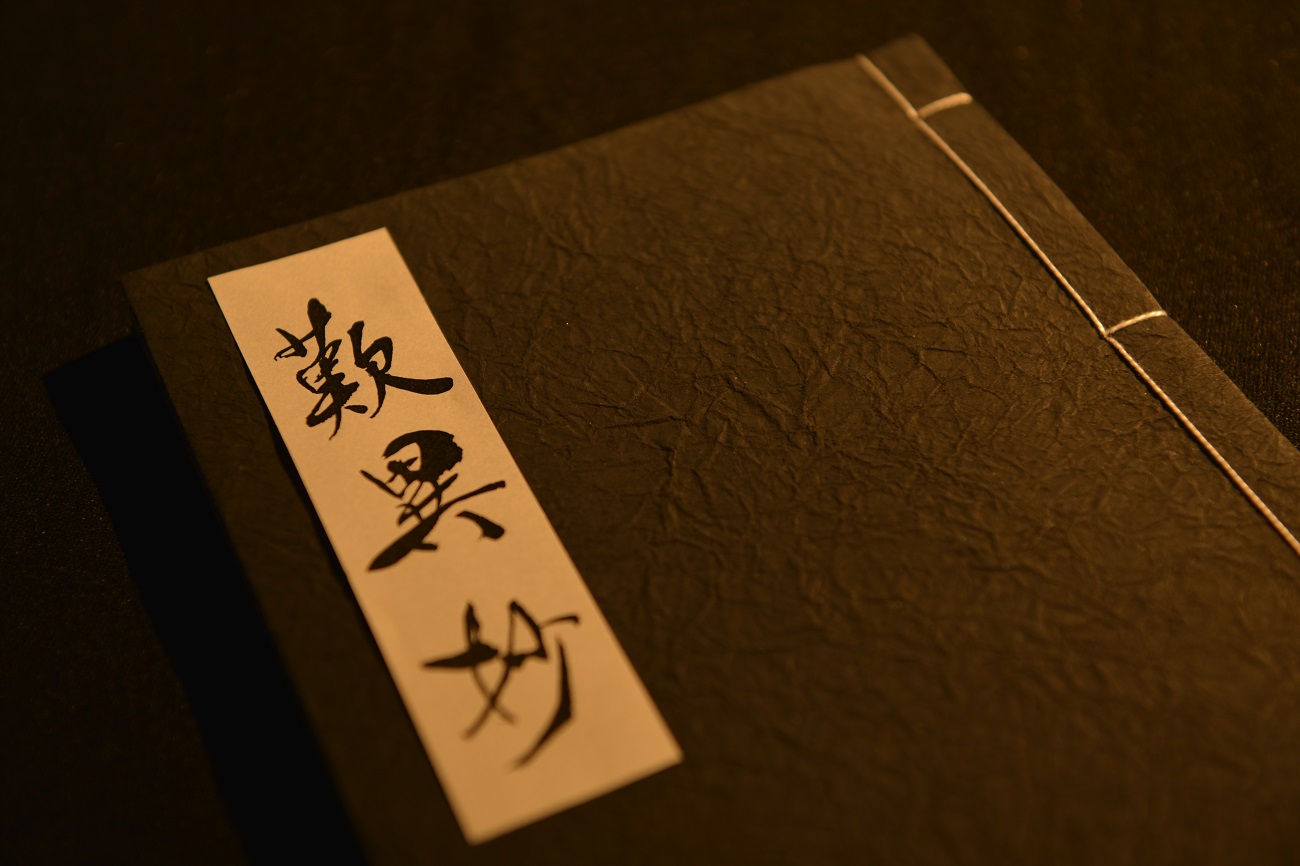
その絶望的な問いに対する驚くべき回答が、日本の古典、鎌倉時代に親鸞聖人の教えを記した『歎異抄(たんにしょう)』の中に示されています。
20世紀を代表するドイツの哲学者、マルティン・ハイデッガーもまた、この思想に深い感銘を受け、「21世紀の文明の基礎となり、世界平和に見通しがつく」と日記に記したと伝えられています。
彼らが注目したのは、『歎異抄』に記されている「摂取不捨の利益(せっしゅふしゃのりやく)」という教えでした。
「摂取不捨の利益」とは、無明の闇がなくなった、絶対の幸福を指します。
決して見捨てられることのない、永久に変わらぬ幸せです。
私たちは、無明の闇の中にあるからこそ、生きる意味が分からず、他者からの評価や社会的な成功といった「相対的」なものさしに頼らなければ、自分の存在価値を確かめられません。
しかし、「摂取不捨の幸福」は、そうした外部の評価とは一切関係のない、真の安心、満足です。
相対の幸福とは全く違う、この絶対の幸福を知る時、私たちは他者との比較ゲームという終わりのない苦しみから、初めて解放されるのです。
そして、この絶対的な安心感は、私たちを陰謀論からの脱却へと導きます。
心の闇がなくなれば、もはや「分かりやすい敵」を作り出して憎悪をぶつけることで、束の間の安心感を得る必要はなくなります。
「あいつらが悪い」という分断の発想ではなく、自分と同じように、誰もが「無明の闇」という苦悩を抱えた苦しみの人間であるという視点が生まれます。
そこから始まるのは、「みんなで幸せになろうよ」という共生の思想です。
世界に満ちる怒り、SNSが加速させる比較地獄、そして不安が生み出す陰謀論と分断。これらの問題は、一見すると複雑に見えますが、その根源をたどれば、私たち一人ひとりの心の中にある、人生の目的が分からぬ「無明の闇」に行き着きます。
『歎異抄』には、その苦しみの根元が解決できた幸福に、全ての人がなれるのだよ、と示されています。
ハイデッガーが予見したように、西洋近代思想が突き当たった限界を超えるヒントが、ここにあるのかもしれません。
もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


