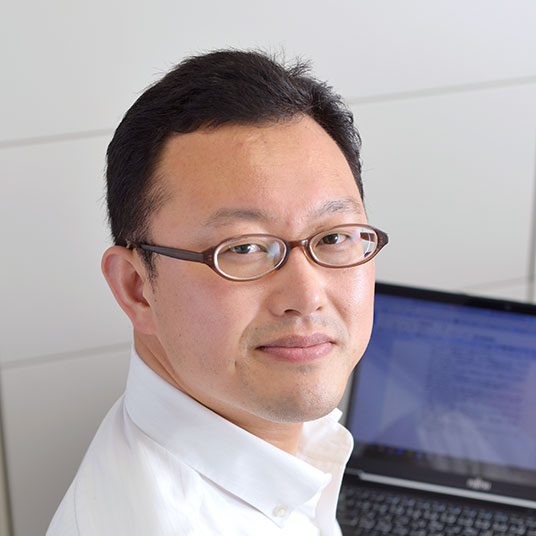
「もう年だから……」なんて、夢をあきらめていませんか?
今回は、江戸時代に日本で初めて実測による全国地図を作り上げた人物、伊能忠敬の物語です。
彼の人生は、何歳になっても挑戦できること、そして目の前のことに一生懸命取り組む大切さを教えてくれます。
「千里の道も一歩から」。忠敬が歩んだ壮大な道のりを、一緒に見ていきましょう。
長かった夢への準備期間|商才とリーダーシップを発揮

伊能忠敬は、少年時代から学問、特に天文学や数学が大好きでした。
しかし、家庭の事情で学者の夢をあきらめなければならなくなります。
17歳の時、千葉県の名家である伊能家に婿養子として入ることになったのです。
当主を失った家の再興という大きな責任を背負い、忠敬は家業である酒造業などに集中することを決意しました。
忠敬は、商売の世界で驚くべき才能を発揮します。
本業の酒や醤油づくりだけでなく、お米の売買、不動産業、さらには江戸で薪や炭を売るビジネスまで手がけ、多角的な経営に乗り出しました。
その結果は数字にも表れており、彼が家業を継いでから約20年で、お店の収益をなんと約3.6倍にまで成長させたのです。
この成功が、後の地図作りのための莫大な資金源となりました。
1783年に浅間山が大噴火し、「天明の大飢饉」が全国を襲った時、彼は地域社会のリーダーとして立ち上がりました。
多くの人々が食べるものに困る中、忠敬は米の値段が上がることを予測し、事前に大量のお米を買い付けていました。
そして飢饉が深刻になると、その備蓄米を惜しむことなく放出し、困っている人々に安く、あるいは無償で分け与えたのです。
さらに、ただ食料を与えるだけでなく、川の堤防を修理する土木工事を起こし、仕事がなくなった人々に働く機会を提供しました。
彼の素晴らしいリーダーシップのおかげで、彼が暮らす村とその周辺では、一人の餓死者も出なかったと伝えられています。
私財を投じて人々を救う姿は、地元で大きな信頼を集めました。
少年時代の夢は一旦横に置きながらも、目の前の仕事に誠実に取り組み、大きな成功と信頼を勝ち得た忠敬。
この30年以上にわたる経験こそが、彼の後半生の偉業を支える土台となったのです。
日本を歩いた17年|地図作りに捧げた後半生は50歳からの再出発!19歳年下の師匠に入門

49歳で家業を息子に譲った忠敬は、ついに少年時代からの夢を追いかける決心をします。
翌年、50歳になった彼は江戸へ向かい、当時最高の天文学者であった高橋至時(たかはし よしとき)の弟子になりました。
驚くべきことに、師匠の至時は31歳。なんと19歳も年下でした。
身分や年齢が重んじられた時代に、大成功を収めた年長者が、息子ほど年の離れた若者に教えを請うのは、異例中の異例です。
しかし忠敬は全く気にせず、誰よりも熱心に天文学と測量の勉強に励みました。
その真摯な姿に心を打たれた至時は、やがて忠敬に敬意を込めて「推歩先生」(推歩とは天体の位置を計算する学問のこと)と呼ぶようになったといいます。
地球1周分の道のりと、驚きの測量技術

当時、忠敬や師匠の至時が最も知りたかったことの一つは、「地球の正確な大きさ」でした。
そのためには、できるだけ長い距離を正確に測る必要があったのです。
ちょうどその頃、幕府は蝦夷地(現在の北海道)に外国の船が頻繁に現れることに頭を悩ませており、国防のために正確な地図を欲していました。
そこで師匠の至時は、「国防のための地図作り」という名目で、弟子の忠敬が蝦夷地を測量するプロジェクトを幕府に提案します。
これにより、忠敬の個人的な探求心は、国家事業という大きな目的と結びつきました。
55歳になった忠敬は、測量隊を率いて江戸を出発します。
費用のほとんどは自己負担で、現在の価値で数千万円にも上ったとされますが、彼は商売で築いた財産を惜しみなくつぎ込みました。
こうして、足かけ17年にわたる日本全国測量の旅が始まったのです。
忠敬たちが歩いた距離は、合計で約4万キロメートル。
これは、ほぼ地球の円周と同じです。
昼は歩いて測量し、夜は膨大な記録を整理。
晴れた夜は天体観測を行い、星の位置から測量のズレを修正するという、過酷な毎日でした。
彼らの測量方法は、ハイテク機器がない時代の知恵と工夫の結晶でした。
まず、2つの地点の距離と方角を測ってつないでいく「導線法」を基本としました。
しかし、これだけでは少しの誤差が積み重なって大きなズレになってしまいます。
そこで、遠くの山の頂上など、複数の場所から見える目標物を決めて方角を測り、地図の上でズレを修正する「交会法」という方法も使いました。
富士山は、38ヶ所もの地点から測量の目標とされた記録が残っています。
そして、最も重要なのが「天文測量」です。
夜空の星を観測して、今いる場所の緯度(地球の北から南のどの位置にいるか)を正確に割り出しました。
この天からの絶対的な情報を基準にすることで、地図全体の精度を劇的に高めたのです。
忠敬は、71歳で全国の測量を終えましたが 、その3年後、地図の完成を見ることなく73歳で亡くなりました。
中心人物を失い、プロジェクトは最大の危機を迎えます。
しかし、弟子たちは師の偉業を絶対に完成させるという強い決意のもと、忠敬がまだ生きているかのように見せかけながら、作業を続けました。
そして1821年、忠敬の死から3年後、ついに『大日本沿海輿地全図』、通称「伊能図」が完成し、幕府に提出されました。
その地図は、現代の地図と重ねてもほとんどズレがないほど、驚くべき精度を誇っていました。
約40年後、測量のために来日したイギリスの測量艦隊が、その正確さに腰を抜かしたという逸話も残っています。
伊能忠敬が教えてくれる、豊かな人生のための3つのヒント
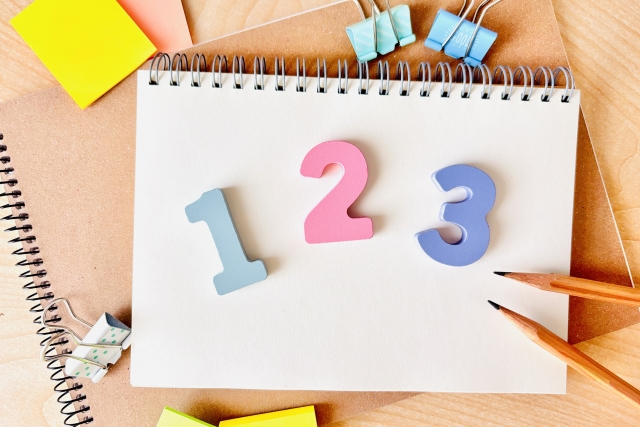
伊能忠敬の人生は、私たちに多くのことを教えてくれます。
第1に、「学びや挑戦に年齢は関係ない」ということです。
50歳から新しい学問を始め、誰もが認める偉業を成し遂げた彼の姿は、何かを始めるのに遅すぎることはないと、私たちを勇気づけてくれます。
第2に、「大きな夢は、地道な準備と実行から生まれる」ということです。
30年以上、商人として、地域のリーダーとして目の前の仕事に全力で取り組んだ「準備」があったからこそ、17年にもわたる測量という壮大な「実行」が可能になりました。
そして最後に、「自分の成功を、他のために役立てる」という生き方です。
私財を投じて人々を飢饉から救い、人生の後半はすべてを国のための地図作りに捧げた忠敬の姿は、とても輝いて見えます。
「千里の道も一歩から」。伊能忠敬が示してくれたように、いくつになっても夢や志を忘れず、今自分ができることに着実に取り組んでいけば、いつか必ず大きな目標にたどり着くことができるはずです。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


