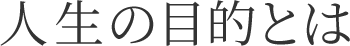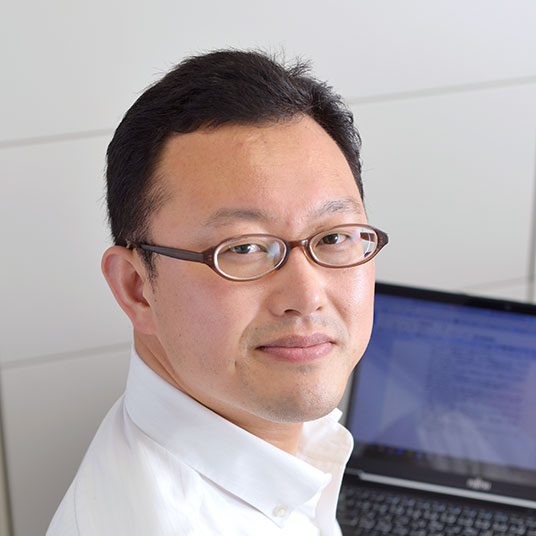
前回に続き、ロシアの文豪ドストエフスキーの長編小説『カラマーゾフの兄弟』が、時代や国を超え、多くの人の心を動かす理由を探ります。
★『カラマーゾフの兄弟』のあらすじなどを知りたい方は、前回の第1回をごらんください。
なぜ、100年以上も前に書かれたこの作品が、今の時代でも色あせないのか。
それは、ドストエフスキーが、他のどの作家にもまして人間の心の実態に迫ったからでしょう。
『カラマーゾフの兄弟』には、味わい深い人間模様が、驚くほどリアルなタッチで描かれています。
読者が、登場人物の姿に自分を重ねてしまうところに、ドストエフスキー作品の醍醐味があります。
ドストエフスキーは17歳の時、兄への手紙に次のように書いています。
人間とは如何なるものか、ドストエフスキーは、生涯をかけて探究し続けました。
「汝自身を知れ」と古代ギリシャの格言にあるように、自分を見失ったまま、どうして真の幸福になれるでしょうか。
自己を正しく知ることは、幸せへの第一歩です。
その集大成とも言えるのが、彼の遺作となった『カラマーゾフの兄弟』です。
財産と女性をめぐる醜い争い

「カラマーゾフ」という言葉には、ロシア語で、「黒く塗る」という意味があります。
ドストエフスキーは意図的に「黒塗りの家系」という意味を、その姓に含ませていたと考えられます。
女好きと強欲こそがカラマーゾフ家の特徴、と言わんばかりに、作品は展開していきます。
カラマーゾフ家を仕切っているのは父親のフョードル・カラマーゾフです。
成り上がり地主であるフョードルは、手に入るものなら何でも手にしてしまうという物欲の権化で、「淫蕩このうえもない男で一生を通した」という人物です。
また、直情的でキレやすい長兄のドミートリーは、情欲にまみれて堕落することこそ本望だとしたうえで、「俺はカラマーゾフだからさ」とつぶやきます。
物語は、おもに財産分与に関する、父フョードルと長男ドミートリーの争いが絶えません。
しかも、グルーシェニカという女性をめぐり、2人が対立関係にあることが、それに拍車をかけていました。
ドミートリーは、カテリーナというモスクワ出の女性と婚約中であったために、問題はさらに泥沼化しています。
おまけに彼は、カテリーナがモスクワに送金しようとした3000ルーブルを横取りし、それをグルーシェニカとの豪遊にあてていたのです。
3000ルーブルとは、今日の貨幣価値でおよそ300万円。
この現金3000ルーブルが、『カラマーゾフの兄弟』では、物語の鍵になります。
登場人物らは信仰の意味など深遠な議論を戦わせる一方で、巨額の遺産や借金など、お金に翻弄されていきます。
こんなセリフのあと、作品は急展開を迎え、登場人物たちのいろいろな思惑が絡み、ついに父殺しにまで発展するのです。
このように、欲望、怒り、嫉妬のうずまく人間関係が、物語を通して描かれているのです。
『カラマーゾフの兄弟』と「貪欲」

『カラマーゾフの兄弟』とは、東洋的にいえば、「煩悩まみれの兄弟」「欲望まみれの兄弟」というニュアンスになるでしょう。
仏教には「煩悩具足の凡夫」という言葉がありますが、すべての人(凡夫)が、煩悩に目鼻つけた存在だといわれています。
万人にある、激しい煩悩を描いたからこそ、『カラマーゾフの兄弟』は、時代や国を超えて読み継がれているのだと思います。
「煩悩」とは、私たちを煩わせ、悩ませるもので、全部で108あります。
その108の煩悩の中で、特に私たちを苦しめるものに、貪欲・瞋恚・愚痴の3つがあり、猛毒のように恐ろしいので、「三毒の煩悩」ともいわれます。
中でも、最初の「貪欲」とは、欲の心。
無ければ欲しい、有れば有るでもっと欲しい、と際限なく求める心です。
願望を実現すれば満たされるように思いますが、その満足感は一時的で、欲望はますます肥大し、「もっと、もっと」と底無しに欲しがります。
テレビや冷蔵庫、エアコン、洗濯機など、今やどの家庭にもある家電製品も、50年ほど前は、それらを手に入れること自体が庶民の夢でした。
既にその夢は実現され、幸せな暮らしをしているはずの私たちですが、今度は有るのが当たり前で満足感がなく、欲しい物は尽きません。
「世の中は 一つかなえば また二つ 三つ四つ五つ 六つかしの世や」と歌われるように、一つ願いがかなっても、また次々と欲望が起きてきてキリがないのです。
この世は、満足ということがありません。
『蜘蛛の糸』は、『カラマーゾフの兄弟』のオマージュ?

このような欲の本質は、自分の利益を最優先する「我利我利の心」です。
“自分さえよければ、他人はどうなってもかまわない”というのが本性だから恐ろしいのです。
普段は隠れていても、生きるか死ぬかの瀬戸際になると顔を出すこの自己中心的な本性を、芥川龍之介は、小説『蜘蛛(くも)の糸』で表現しました。
実は、『カラマーゾフの兄弟』には、この芥川の小説と、そっくりな話が出てきます。
切れてしまうのは、蜘蛛の糸ではなく、1本のネギ、ですが、どうやら、ロシアの農民に伝わるおとぎ話だったようで、芥川も、この話に影響を受け、名作『蜘蛛の糸』を執筆したとされています。
洋の東西を問わず、我利我利の本性は変わりません。
会社が経営不振で多額の借金を抱え、困り果てた経営者が、小学四年の実の娘に生命保険を掛け、知人と共謀し、交通事故に見せかけて殺害したという事件がありました。
こんな悪魔の所業も、我利我利の欲の心の仕業なのです。
朝から晩まで、底知れぬ欲に引きずり回され、苛まれているのが私たちの実態です。
この欲で、罪を造らない人は、果たしてあるのでしょうか。
ドストエフスキーは、読者の代表として描く三男のアレクセイに「僕にもカラマーゾフの血が流れていますからね」と言わせ、次のように叫ばせています。
この大長編を読み終えたとき、欲望にまみれた「カラマーゾフ家の血」のようなものが、自分の中にも流れていることに気づくかもしれません。
ドストエフスキーが生涯、問い続けたのは、「人間は所詮、欲の塊にすぎないのか。もしそうならば、罪を重ねてなぜ生きるのか」という、根源的な問いでした。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから