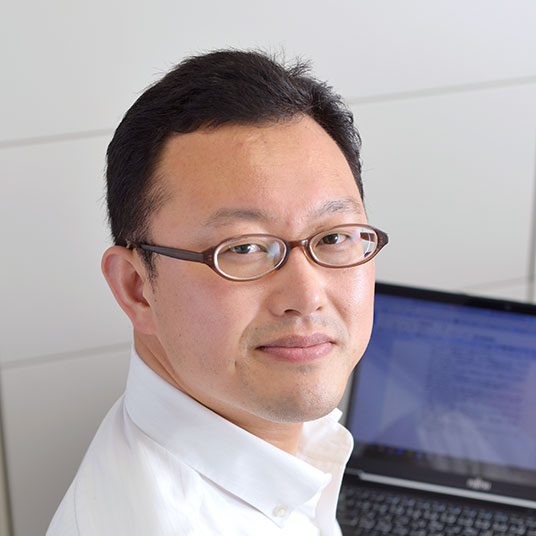
『カラマーゾフの兄弟』は、ロシアにとどまらず世界の文学を代表する文豪ドストエフスキー(1821-1881)の、遺作にして、最大の長編小説です。
長い上に、超難解といわれ、多くの人が「読みたいけど無理そう・・・」「難しくて理解できなさそう・・」と思うはずです。
しかし、新潮文庫版の『カラマーゾフの兄弟』は、帯に「上巻読むのに4ヶ月。一気に3日で中下巻! 」という、芥川賞作家・金原ひとみのコメントが書かれ、話題になりました。
ちょうど、哲学書と恋愛小説と推理小説を足して重厚にした感じで、中盤から急激に面白くなります。
英作家サマセット・モームは、「世界の十大小説」の1つとしてこの作品を挙げました。
「小説の最高傑作」「すべての小説は『カラマーゾフの兄弟』に含まれる要素でできている」など、古今東西の小説の中で最高傑作といわれるのが、『カラマーゾフの兄弟』です。
時代や国を超え、この作品が多くの人の心を動かす理由を、数回にわたって探ってみましょう。
『カラマーゾフの兄弟』を愛読する有名人

『カラマーゾフの兄弟』を愛読する有名人は、枚挙にいとまがありません。
何人か、挙げてみましょう。
アインシュタイン
20世紀最大の物理学者と言われるアルベルト・アインシュタインは、「ドストエフスキーは数学者カール・フリードリヒ・ガウスよりも大きく、精神性のミステリーに挑戦した偉大な宗教的作家」と評しました。
フロイト
精神分析学の父とも呼ばれるオーストリアの精神科医ジークムント・フロイトは、『カラマーゾフの兄弟』を「最も壮大な小説」と称賛し、ドストエフスキーの文学に強い興味を寄せています。
論文「ドストエフスキーと父親殺し」で、ドストエフスキーの小説や登場人物について研究しているほどです。
フロイトが論文の表題に作家の名前を冠したことは、極めて異例なことだと言われています。
ウィトゲンシュタイン
イギリス・ケンブリッジ大学で教鞭をとった、20世紀最大ともされる哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは、『カラマーゾフの兄弟』を50回以上も熟読したといいます。
第一次世界大戦従軍時の数少ない私物の一つが『カラマーゾフの兄弟』でした。
ニーチェ
20世紀思想に決定的な影響を与えた哲学者フリードリヒ・ニーチェはドストエフスキーを「唯一無二の心理学者」と呼び、『カラマーゾフの兄弟』を読んで「私の人生で最も美しい幸運の一撃だった」と述べました。
黒澤明
映画監督の黒澤明は「もちろん僕などドストエフスキーとはケタが違うけど、作家として一番好きなのはドストエフスキーですね」と語り、若い頃から熱心に読んでいたといいます。
村上春樹
毎年のようにノーベル文学賞の有力候補と目され、著作が世界中で愛されている作家の村上春樹さんは、最も好きな作品の一つとして、『カラマーゾフの兄弟』を挙げ、4回は読んだと公開インタビューで語っています。
「世の中には二種類の人間がいる。『カラマーゾフの兄弟』を読破したことのある人と、読破したことのない人だ」とまで言うほどです。
そのほか、作家のカフカ、ヘミングウェイなど、世界中に影響を与えました。
俳優のキアヌ・リーブスも、『カラマーゾフの兄弟』を愛読しています。
日本でも、江戸川乱歩、小林秀雄、手塚治虫、大江健三郎、三島由紀夫、太宰治などが愛読し、ドストエフスキーから強い影響を受けています。
【ネタバレ注意!】『カラマーゾフの兄弟』のあらすじ

それでは、『カラマーゾフの兄弟』のあらすじを紹介しましょう。
物語は、カラマーゾフ家の「父と3人の息子たち」の間で複雑に絡み合う人間模様や、2人の美女をめぐる愛憎劇などを中心に描かれます。
ロシアの田舎町に居を構える地主フョードル・カラマーゾフには、先妻との子である長男ドミートリーと、後妻との子である次男イワン、三男アレクセイ(アリョーシャ)の3人の息子がいます。
このほか、カラマーゾフ家には、料理人として仕えるスメルジャコフらが住み込んでいます。
スメルジャコフの実父はフョードル、という噂もありました。
豪放磊落、直情的な性格のドミートリーは、遺産相続や妖艶な美女グルーシェニカをめぐって、父と激しく対立。
ドミートリーには婚約者カテリーナがおり、金銭的な負い目もあって、婚約を破棄できずにいます。
理知的で無神論者のイワンは、そのカテリーナに思いを寄せ、彼女を冷たくあしらう腹違いの兄に、強い憤りを覚えます。
優しい性格で誰からも愛されるアリョーシャは、町外れにある修道院で修行を積みつつ、彼らの仲裁に入ります。
そのアリョーシャは、ゾシマ長老を敬愛してやみませんが、ゾシマの死後、彼の遺体をめぐる事件に激しく動揺してしまいます。
物語は、父フョードルの殺害と、その犯人捜しで急展開を迎えます。
フョードルの遺体が発見されると、真っ先に嫌疑がかかったのがドミートリーです。
2人がグルーシェニカを争い、激しくケンカする様子が何度か目撃されていたからです。
ドミートリーは逮捕され、一貫して無罪を主張するも、受け入れられません。
裕福なカテリーナは、ドミートリーを犯人と考えていましたが、裁判では減刑を望み、弁護士をつけます。
一方、ドミートリーへの愛に目覚めたグルーシェニカと、心優しいアリョーシャは、無罪を信じて疑いません。
これに対して、イワンは当初、兄の犯行を確信していましたが、自分に心服するスメルジャコフと面談を重ねるうち、思いもかけない真犯人にたどり着きます。
しかし、裁判の行方のカギを握るスメルジャコフが判決前に自殺。
彼に多大な影響を与えていたイワンも、罪の意識から発狂していくのです。
ついに、ドミートリーに運命の判決が下されるのでした――。
『カラマーゾフの兄弟』と人生の目的

なぜ、『カラマーゾフの兄弟』は、多くの人を魅了するのでしょうか。
もちろん、様々な意見があるでしょうが、私は、『カラマーゾフの兄弟』が、「人は、何のために生きるのか」という、私たちが最も知りたい問いに、真摯に向き合った作品だからではないか、と思います。
以下の言葉には、そのことが端的に表れているのではないでしょうか。
第2部の第5編「プロとコントラ」は、ドストエフスキーの思想の精髄と言われる作中劇『大審問官』が語られる、重要な場面です。
当時の『ロシア年鑑』によると、1868年以降の5年間で、自殺者が3倍に増えたという恐ろしい数字が出ており、ドストエフスキーは「じっさい、わが国では近年自殺が増えて、だれももうそのことを話題にしないほどになっている」(『作家の日記』)と述べています。
同時代のロシアにはびこる「自殺病」から人々を救うため、一作家として何かを語らなくてはならない。
何らかの救いの道を提示しなければならない。
そうしたギリギリの想いから紡ぎだされた物語が、やがて『カラマーゾフの兄弟』に結実したのではないかと、ドストエフスキー研究者・亀山郁夫さんは示唆しています。
作中で自殺するスメルジャコフについては、改めて取り上げたいと思います。
なぜ自殺してはいけないのか
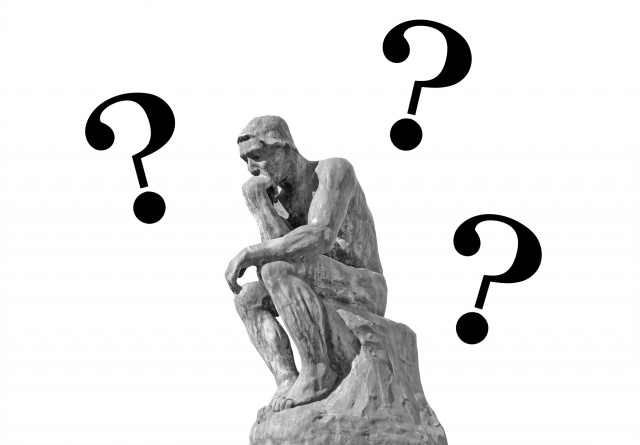
自殺は、哲学における中心的な問題の1つです。
実存主義の作家として有名なカミュは『シーシュポスの神話』という哲学的エッセイの冒頭で、こう書いています。
自ら命を捨てる人は、現代も後を絶ちません。
日本の自殺者数は、年間2万人を超えます。
かつて自殺未遂は、自殺者の10倍といわれていましたが、今や20倍という調査結果が出ています。
「こんなことなら死んだほうがマシ」と思いながらも、「死ぬのは怖い」「家族に迷惑をかける」と踏みとどまっている人は、数百万どころではないでしょう。
地球より重い命が、いとも簡単に捨てられている根本原因は、どこにあるのでしょうか。
それは、人間に生まれなければ果たすことのできない、崇高な目的のあることを知らないから、と言えるかもしれません。
2600年前、釈迦は「人生は苦なり」と道破しました。
それは19世紀のロシアも、現代の日本も、少しも変わりません。
物価高、夫婦の亀裂、介護の重圧、突然の事故や病気、災害など、想定外の苦悩が次から次へとやってきます。
ただ苦しむだけの一生に、どんな意味があるのか。
人生には、どんなに苦しくとも果たさねばならぬ、大事な目的がある。
だからこそ、人命は無限に尊いと説かれるのが仏教です。
ぜひ、こちらの記事もごらんください。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


