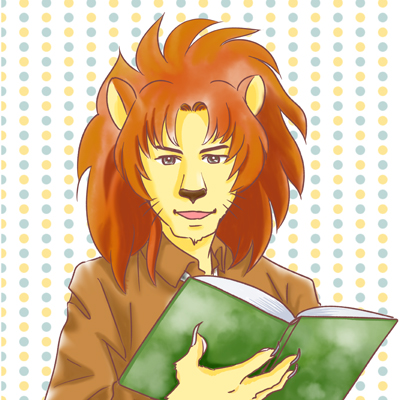
いま、異世界転生モノが流行っています。ファンタジーも流行しています。
例えば、ライトノベルでは「異世界転生モノ」が今大流行です。
この中でも目立つのは、1位の『転生したらスライムだった件』。この作品を筆頭に「異世界転生系」と呼ばれる作品は、書店の漫画やライトノベル売り場の一角を占めるほどになっています。
出版科学研究所によると、タイトルに「異世界」「転生」を含む作品は平成25年までは年間10点ほどでしたが、26年には128点に急増し、30年には、過去最高の567点になりました。
タイトルでは「異世界転生」をうたわない作品もありますから、実際はさらに多いといわれています。
また、世界的にはハリー・ポッターなどファンタジー人気も加熱しています。
第1巻『ハリー・ポッターと賢者の石』は、ロンドンのブルームズベリー出版社から1997年に刊行されました。
当時のJ・K・ローリングさんは全く無名の新人。その初作であるにもかかわらず、瞬く間に世界的ベストセラーになったのです。
子供のみならず多数の大人にも愛読され、児童文学の枠を越えた人気作品として世界的な社会現象となりました。
73の言語に翻訳された本作のシリーズ全世界累計発行部数は、昨年末の時点で5億を突破しており、史上最も売れたシリーズ作品です。
今年7月には、スマートフォンの位置情報サービスを利用した、拡張現実を利用したゲームアプリ「ハリー・ポッター:魔法同盟」(通称ハリポタGO)も登場し、話題になっています。
異世界転生モノが流行るのはなぜか?
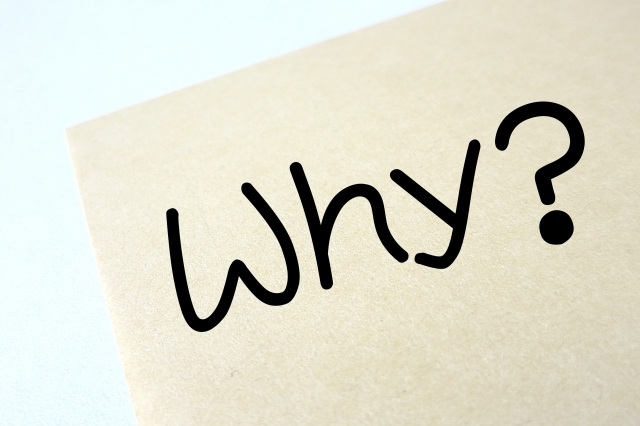
異世界転生モノが流行る理由を、若者論に詳しい社会学者の中西新太郎・関東学院大教授は次のように分析しています。
異世界で冒険ではなくスローライフを送る作品が多く、ほのぼの日常を現実ではなく異世界に求めている。(『朝日新聞』令和元年7月2日)
また、ボストン・コンサルティング・グループで戦略策定などに従事した、作家の山口周さんも、「イギリスが良質なファンタジーを生み出し続ける理由は、現実的であるがゆえの反作用」(ダイヤモンド・オンライン)とコメントしていました。
異世界転生モノが流行るのも、英国発の大ヒットファンタジー『ハリー・ポッター』シリーズが流行ったのも、「冴えない現実からある日、突然抜け出した先には、自分が輝く、なりたい自分になれる世界が待ってる!」のお手本だからです。
ファンタジーに夢中になっている時には、物語に夢中になり〝目の前のこと〟しか考えていません。
「あんなひどいことを言われた」
「先生から叱られた」
「嫌いな人と今日も会わねばならない」
などの、日常のもやもやした感情に煩わされないのです。
ファンタジーの生まれる背景に生きづらさ

しかし、考えてみると、ファンタジーにつながる分野は、洋の東西を問わず昔からあります。
実写化されて有名な「アラジン」も元はアラブの国王に、シェヘラザードという后が1001夜、語ったとされる幻想物語が元になっています。
東洋では西遊記や三国志演義、封神演義などが有名です。
日本では最古のファンタジーというと竹取物語、かぐや姫の物語ですね。世界最古のファンタジーとしては、古代メソポタミアのギルガメッシュ叙事詩が挙げられていました。
中でも、有名なファンタジー小説の原点といえば、イギリスの数学者チャールズ・ドジソンが1865年にルイス・キャロルの筆名で書いた児童小説『不思議の国のアリス』が上がります。
幼い少女アリスが白ウサギを追いかけて不思議の国に迷い込み、しゃべる動物や動くトランプなどと出会いながらその世界を冒険するさまを描いています。
その誕生の経緯について書かれた本『「不思議の国のアリス」の誕生』(ステファニー・ラヴェット・ストッフル著、創元社)によると、ルイス・キャロルは、川下りの舟の中の退屈な時間を過ごすため、キャロルは一緒にいた知人の三姉妹の1人、アリスに対して、同じ名前の少女の冒険物語を即興で語って聞かせたそうです。
アリスが喜びそうなものを出して、その世界の中で、興味の赴くまま行動させ、その結果を説明して……というように、ストーリーは展開します。
アリスにぜひ、と頼まれたキャロルが、この物語を手書きの本にして彼女にプレゼント。
その後、知人たちの好評にも後押しされて出版に踏み切ったといわれます。
こうして誕生した本が、イギリスでは、あのシェイクスピアに次ぐ、児童文学の巨塔となりました。
『不思議の国のアリス』の誕生した時代背景

『不思議の国のアリス』が書かれた当時のイギリスは、ヴィクトリア朝とも言われ、イギリス史上、最も繁栄した時代と言われます。
産業革命の結果、国中に鉄道網がはりめぐらされました。
一方で、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』が発刊され、それまでのキリスト教的なものの考え方も、大きく揺らいだ時期です。
過酷な労働環境に苦しむ人があふれ、「切り裂きジャック」などの世間を揺るがす事件も起きました。
科学を発展させれば幸せになれると信じられた時代に、影が差し始め、生きづらさがあふれていた。
『不思議の国のアリス』は、そんな閉塞した時代のファンタジーなのです。
『不思議の国のアリス』に、こんなシーンがあるのをご存知ですか?
チェシャ猫「それは君がどこに行きたいかによるね」
アリス 「どこだっていいんだけど・・・」
チェシャ猫「だったら右に行ったって、左に行ったって一緒さ」
アリス 「どこかへ辿り着きたいのよ」
チェシャ猫「だったらどこかへ辿り着くまで歩けばいいのさ」
どっちへ行きたいか分からなければ、どっちの道へ行ったって大した違いはありません。
たどり着きたい目的地がハッキリしないのに、「道に迷った」と訴えるアリスに、チェシャ猫の言うことは論理的です。
「不思議の国」では何もかもがおかしな状態です。
「子供向けの話なんだから、破茶滅茶でもいいじゃないか」という人もありますが、普段、論理を重視していた数学者キャロルにしては、不自然です。
これについて、学者の中には、「論理だけでは説明できない、不条理を示しているのだ」と分析する人もいます。
洋の東西を問わぬ生きづらさ

ファンタジー同様、生きづらさを述べた名言も、洋の東西を問わず昔からあります。
例えば、ドイツの哲学者ニーチェは
といい、中国・唐の時代、長安を中心に活躍した、善導大師という高僧は
インドではブッダのさとりを開かれた第一声は
であり、人生を「娑婆」とおっしゃっています。
娑婆とは昔のインドの言葉で、「堪忍土」を意味します。
堪忍とは「こらえ、しのぶ」と書きます。
明治の文豪・夏目漱石も「草枕」という小説でその「生きづらい」人の世をこのようにいっています。
情に棹差せば流される
意地を通せば窮屈だ
とかくこの世は住みにくい
向こう三軒両隣
普通の人が住んでいる
住みにくいからと逃げ出せば
人でなしの国にでも行くしかない
それだけ現実の世は草枕でいうように「人の世」は
・正論と正論の激突
・周りの感情に流され流され
・意地と意地のぶつかり合い
で、堪忍していかねば生きていけません。
「生きづらい世の中」と漱石が論じた通りではないでしょうか。
草枕ではその後、次のように続きます。
この生きづらい人の世が”住みにくいからと逃げ出せば「人でなしの国」へでも行くしかない。”
だから「人でない国」=「ファンタジーの世界」に人は旅に行くしかないと漱石は論じます。
せめてしばしの間でも「人にあらざる世界」に転生して「夢」を見させてもらいたいということなのでしょう。
生きづらいのは、昔も今も、場所も関係なく、変わらないのですね。
生きづらさを根本から解決するには?

しかし「夢見られた夢」は一時的で、必ず覚める時が来ます。
趣味や生きがいの喜びは、しばしの興奮やスリルを味わえる楽しいものですが、楽しい「ひととき」が終わってしまえば、嫌な宿題、やり残した勉強、たまったゴミと、むなしくつまらない現実に逆戻り。
有名なゲーマーが、ゲーム中は喜々としていたのに終わると気難しく、つきあいにくかったり、映画を楽しんで見ていた人が、上映が終わり、部屋のライトが付くと、余韻に浸る間もなく次の映画の準備のため、追い出されて不機嫌になるといわれるのも、そのためでしょう。
ノーベル文学賞を受賞したB・ラッセル『幸福論』には「趣味に熱中する楽しみとは、苦痛を一時的に忘れる時間つぶし」とあります。
対症療法ではなく、生きづらさを根本的に解決する必要があるのではないでしょうか。
ではその根本解決とはどういうことでしょうか。
詳しく知りたい方は、こちらをごらんください。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


