
カフェ勉強会・おしゃべり会(インスタグラム)
名古屋開催/初心者大歓迎♪
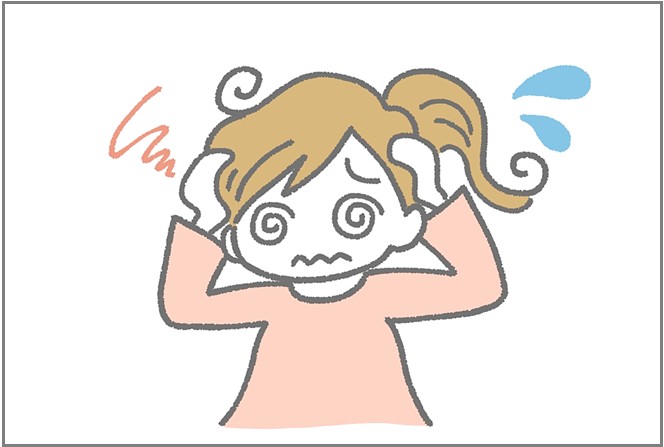

今回はこんなお悩みについてです。
その気持ち、よくわかります。
しらけた空気、微妙な反応、既読スルー。
「なにか間違えたかな」「失敗したな」と思うことってありますよね。
さらに、わかりやすく失敗してしまったときは、
注意、指摘、言われたくなかったひとこと……。
「反省して次に行こう」と割り切ろうとしても、どうしても落ち込んでしまいますよね。
落ち込むことは、人間にとって自然な反応だと思います。
一時的な落ち込みで済めば、あくまで「自然な反応」なのですが、いろいろな条件が重なると、落ち込みが長引くことがあります。
こんなふうに落ち込んでいるときは、反省どころではなくなってしまいます。
こじらせると、八つ当たり、無気力、依存症、身体化など、悪化するリスクもあります。
この場合は、どこかでストップをかけたいですね。
落ち込んでもいい。
そこから回復する術を一緒に身につけましょう!
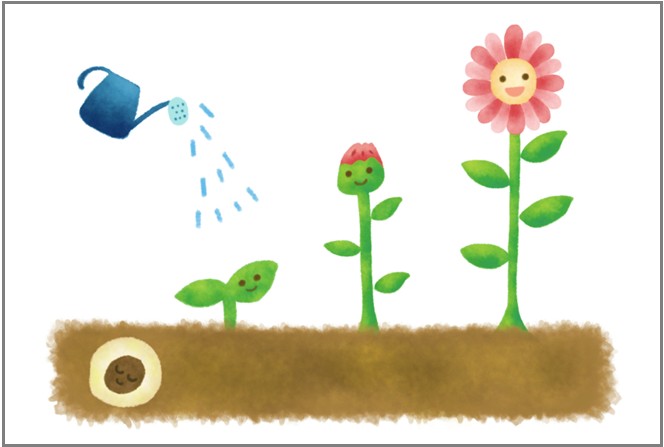
落ち込みから回復するスピードは人それぞれ。
「立ち直りが早ければいい」というものでもありません。
早く立ち直ろうと無理する必要はありませんが、落ち込みが長期化すると、病気になってしまうこともあります。
生きていれば病気になることだってあります。
ただ、病気になってしまうと、回復にかなりの時間を要します。
普段からケアをして、できるだけ病気にならないようにしたいものです。
たとえば、植物を育てるときも、病気にならないように、気をつけることがあります。
植物でさえ、病気にならないために、これだけ気をつけるのです。
人間だって同じ。体と心をととのえていなければ、病気になってしまいます。
さらに猛暑の対処や、誰と接するか、どんな仕事をするか、趣味など、元気でいるための条件はいろいろありますね。
しかも、元気でいる方法は、人それぞれ違います。
植物で考えるとわかりやすいのですが、何をすれば元気になるのか、種類によって異なります。
方法が真逆の場合もあります!
特性をよく知り、適材適所、対処することが不可欠です。
人間も、それぞれ自分に合った方法でなければなりません。
あの人は元気になった方法でも、あなたはよけいに元気をなくすかもしれません。
今回は「落ち込みやすい人」のケアの方法を掘り下げていきます。

そんなタイプの人もいますが、今回は落ち込みやすい人向けの内容ですから、「落ち込まなくていい3つの理由」を書いていきます。
落ち込みやすい人が、反省して向上につなげるには、落ち込みから回復する必要があります。
ズルズルと落ち込みの泥沼から抜け出せないときは、この3つを読み返してみてくださいね。
そう思うときでも、案外、人は気づいていません。
あなたの熱狂的なファンでない限り、さほど気にしてないものです。
あなた自身が「自分」の熱狂的なファンだから、一挙手一投足が気になるんです。
そこまで落ち込まなくていいんです。
あなたの失敗に、周囲の人が困った様子だったとしましょう。
そう思うときでも、大丈夫。
みんなすぐ忘れます。
どうしても気になるかもしれませんが、人の心はすぐに変わります。
次の関心事に移るからです。たとえば、
それくらい、人の心は一瞬で変わるのです。
有名人のトップニュースでさえ、関心は続きません。
昔から「人のうわさも七十五日」と言うではありませんか。
仏教では「諸行無常」と説かれ、あらゆるものは移り変わると言われています。
そこまで落ち込まなくていいんです。
みんなそうではないでしょうか。
自分のことが一番大切。
自分のことが一番心配。
優しい人でも、他人のことは、ときどき思い出すくらいでしょう。
親子でさえ、離れていたら忘れてしまいます。
だからこそ、人を助け、人の長所を見つけて褒め、誰かの役に立つことをすれば、「あら、案外いい人ね」となります。
そこまで落ち込む必要はないんですよ。

落ち込む出来事があってから対処しようとしても、気がついたら泥沼にハマっていた……となりがちです。
そもそも「失敗しない人間になる」なんて、ふつうはできません。
「失敗しても大丈夫」な土台を作るための、「日頃の心がけベスト3」を列挙しますので、ぜひやってみてくださいね!
日頃から、相手の良いところを見つけて、言葉で伝えていると、
と思ってもらえることが多いです。
好きな人の失敗なら、人はそう悪くとらえません。
と善意に解釈してもらえるのです。
信頼貯金をコツコツためておきましょう。
自分の悪いところを気にしすぎて落ち込むのは、
「他人の悪いところを、心の中で批判しているから」かもしれません。
脳は主語を区別することができないので、
「きっと私も批判されているにちがいない」と思うようになります。
相手の悪いところは、よく見えるものですが、流すようにしましょう。
自分の悪いところも、許せるようになります。
そう思うかもしれませんが、当たり前なんて1つもありません。
「失敗しても大丈夫」になるには、自信の貯金が大切。
落ち込んで、自信がマイナスになっても、貯金があれば赤字にならずに済みます。
他人との信頼貯金と同じように、自分との信頼貯金もためておきましょう。
自信が育つ、具体的な方法を2つ挙げます。
落ち込んだ時に、褒めてもらった記録を読み返すと、「自分もそこまで悪くない」と回復が早まります。
そう感じることもありますよね。
ですが、案外、感謝されたり、褒めたりしているものです。
よくよく注意して見つけてみてください。
できなかったことばかり気にしがちですが、できたこともあるはずです。
よくそういう方にお会いします。そう感じるのですよね。
ですが、本当にそうでしょうか?
朝起きた、顔を洗った、洗濯した、栄養のあるものを食べた。
会社に行った、挨拶できた、仕事も着手できた。
よく見れば、何かできたことがあるはずです。
0か100ではなくて、20でも30でも、できた部分は認めること。
自分の「落ち込みメガネ」で色をつけて見ると、できなかったことしか見えません。
そうではなく、できたことはできたと、日頃から、ありのままを正しく見る練習をしましょう。

批判され、否定的にとらえられることもありますよね。
「人の間」と書く人間は、関係性の中で生きている社会的な動物なので、どうしても他人からの評価を気にします。落ち込むのも当然です。
ですが、他人の評価なんて、あてにならないもの。
美術館でとても人気のある、モネ、ドガ、ルノワール。
フランス印象派といわれる彼らは、当時、ひどい批判を浴びました。
しかし、あきらめずに売り歩いた画商の支えなどにより、数年後には、評価されるようになります。
それで話は終わりません。
お互いを評価していた同志たちは、やがて分裂していきます。
「今日ほめて 明日悪く言う 人の口 泣くも笑うも ウソの世の中」
と、禅僧・一休も笑っています。
コロコロ変わる評価に合わせていたら、自分を失ってしまいます。
誰かを傷つける、なにか危険があるなど、自分に直すべきところがあるのなら、そこは反省すべきでしょう。
ですが、落ち込みやすいあなたは、どちらかというと、人を傷つけないように、危険にならないように、気をつけているタイプではないでしょうか。
気をつけて起きてしまったことは、仕方のないこともあります。
批判的、否定的なことを言う人の課題かもしれません。
批判され、否定的にとらえられたときは、境界線を引いて、課題を分離していきます。
相手が直すべきところは、相手の課題。
相手の言い方・態度・価値観などは、相手の課題であって、あなたの問題ではありません。
と見極めるようにしましょう。
それだけで、ショックは半減するはずです。
落ち込みが少し和らぐでしょう。
相手の課題は差し引いた上で、残った「自分にできること」に集中します。
あなたは、あなたの課題とだけ向き合えばいいのです。

日頃から、自分への信頼貯金をためようとしても、なかなかできない人がいます。
自分の良いところを見て充電するより、自分の悪いところを見て放電するスピードのほうが速いからです。その根っこには、
という不安感が強くあります。
失敗を恐れて、自由にふるまうことができません。
あなたがこのタイプなら、「日頃の心がけ」に取り組んでも、効果を感じるまでに年単位で時間がかかるかもしれません。
私もそういうタイプでした。
幼少期からの傷つき体験があって、どうしても「落ち込みメガネ」で物事を見てしまうのです。
「失敗」を、親がどう意味づけて伝えるか。
それによって、子どもは「失敗」の捉え方を学習します。
さらに、私は影響を受けやすいタイプ(HSP)なので、親からのマイナスの言葉が、深く心に刺さって抜けませんでした。
あなたの不安が強い理由も、幼少期にあるのかもしれません。
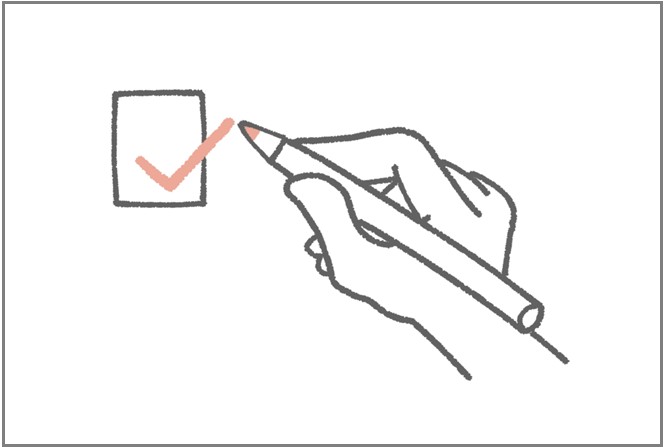
不安が強いタイプの人には、2つの対処法があります。
大人になった今、よくよく考えてみると、親が子どもにどのように教えたかは「親の課題」です。
子どもの問題ではありません。
私がいつまでも背負い続ける必要はないのです。
子どもは失敗するもの。
最初から何でもできる完璧な人間なんて、存在しません。
立場を入れ替えて、視点を変えてみましょう。
私が親なら、子どもに対して
こうやって子どもに接し、寄り添って育みたいと思います。
もちろん現実は、仕事と家事の多忙さで、そこまでの余裕がないかもしれません。
嵐のような毎日に、イライラして怒ってしまうこともあるでしょう。
こう考えてみると、自分の親についても「余裕がなかったんだな」「子育てのスキルが不足していたんだな」と思います。
親の言葉がよみがえってくるかもしれませんが、「親の課題」と切り離しましょう。
あなたはもう、考え方を変えていいのです。
HSPという特性をもって生まれてきたことを、損しているように感じ、嘆いていた時期もありました。
でも、大人になった今、自分で上手に使いこなせばいいと気がつきました。
「影響を受けやすい」のは、悪いことだけでなく、良いこともあります。
こういったことからも、影響を受けやすいのです。
どちらを選ぶのかは、あなた次第です。
私は幸せに生きたいと思います。
子どもは親の影響を受けやすいので、あなたの不安が強くなったのは、あなたのせいではありません。
その時の古傷は痛むかもしれない。
けれど、これからは、あなたの人生です。
良い影響があるものを、どんどん自分の中に取り込み、栄養にしていきましょう。
年単位で時間はかかったとしても、必ず回復します。
なかなか効果が見えなくても、日頃のケアを続けることが大切です。
あなたの血肉となり、自分らしい人生を歩めるようになります。

そんな気持ちが出ることもありますよね。
けれど、一概に誰のせいとも限りません。
それに、不安が強いのは悪いことばかりではありません。
こう言うと驚かれますが、私も、今でも不安感が強く出ることはあります。
けれど、むしろそれでいいと思っています。
不安にはなるけれど、相手に確認してみると問題ナシ。
「悪くとられなかった(ワーイ)」と喜べます。
なかには悪くとらえる人も、存在します。
でも「悪くとらえられるかも」という前提に立っているからこそ、「そういうこともやっぱりあるよね」と、想定の範囲内。
苦手な人もいるからこそ、善意に解釈してくれる貴重な友達に、感謝して喜ぶことができます。
普段から、いい関係でいれば、失敗しても善意に解釈してもらえます。
もちろん、そのために関係をつくるわけではありませんが、まちがいだらけの自分だからこそ、日頃の小さな善い行いを大切にしよう、と心がけることができます。
「悪く見られるんじゃないか」という不安が強いからこそ、
とする、きっかけにもできるのです。
と考えることもできるから、
言葉を吟味し、
相手を思いやり、
気づいたら謝ることができます。
「謝ってくれたらいいよ」と、大抵の人は許してくれるものです。
あなたが思っているよりも、案外、周囲といい関係を築いているのではないでしょうか。
「マイナス思考」で落ち込みやすい性格も、そんなに悪いことばかりではないと思います。

ですが、過去の意味づけを変えることはできます。
幼少期の傷つき体験があるからこそ、学んだこともあるでしょう。
「優しい友達に恵まれて、幸せだなぁ」と、今ある幸せを感じることもできます。
時間はかかっても、自分の糧にして、いい人生のもとにすることもできます。
最近あった出来事も、起きてしまったことは、もう過去のこと。
過去は変えられません。
その失敗には意味があったことになります。
無理に意味をもたせるのではなく、そう思えるときが来ます。
同じことを繰り返す、そんな毎日を過ごすだけでは、そう思える日は来ないかもしれません。
仏教ではこれを「流転輪廻」といいます。
「輪廻」と聞くと、死後、別の世界に生まれることを思い浮かべるかもしれませんが、生きている今もあります。
流転も輪廻も同じことで、車輪が回り続けるように、同じ円周上をぐるぐる回っている状態です。
行けども行けどもゴールはありませんし、そこを出ることもできません。
「人生には目的(ゴール)がある」と教えられているのです。
本当の人生の目的を達成したとき、一切の苦労は報われ、流した涙の一滴一滴が、真珠の玉となってあなたの手に戻ってきます。
それはお釈迦様が丁寧に教えられています。
あなたの落ち込んでいる時間を、人生の目的を考える時間に変えてみませんか?
↓↓↓↓
月見草のカフェ勉強会・おしゃべり会も開催中です。ぜひお会いしてお話ししましょう。
↓↓↓↓
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから

生きる意味やヒントを見つけるための特集ページです。