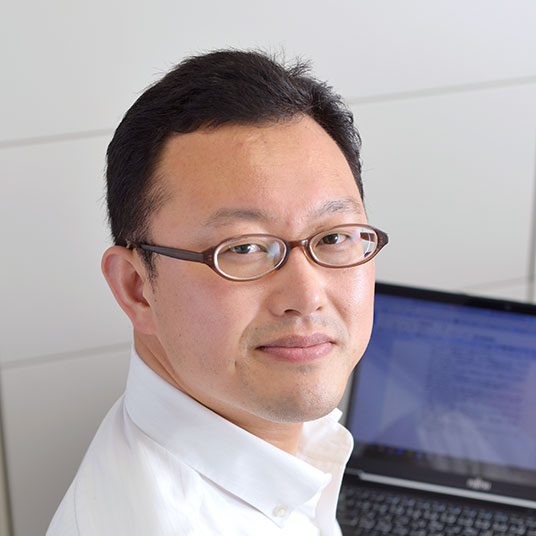
「渡辺崋山(わたなべかざん)」という名前をご存じでしょうか。
もしかしたら、歴史の教科書で一度は目にしたことがあるかもしれませんが、多くの方にとっては、あまり馴染みのない名前かもしれません。
江戸時代後期に武士として、また思想家として生きた人物ですが、彼の最大の功績の1つは、間違いなく「画家」としての側面にあります。
彼が描いた肖像画は国宝に指定されるなど、その筆力は高く評価されていますが、驚くべきことに、彼は幼い頃から絵画の英才教育を受けていたわけではありません。
むしろその逆で、彼の人生は、現代の私たちが想像する以上に過酷な「逆境」からのスタートでした。
絵で家族を救う。逆境から生まれた「描く」ことへの渇望

崋山は1793年、江戸の田原藩(現在の愛知県東部)の武士の家に長男として生まれました。
武士の家と聞くと、裕福な暮らしを想像するかもしれませんが、当時の渡辺家はまったく違いました。
崋山を筆頭に8人もの子供が次々と生まれ、ただでさえ家計は苦しかったのです。
さらに、一家の大黒柱である父は病弱で、薬代がかさむばかりでした。
その暮らしぶりは凄まじく、記録によれば、畳は破れ、冬でも家族全員分の布団さえなかったといいます。
寒さに凍える夜、母は布団で寝ることもなく、机に突っ伏して仮眠を取るのが日常だったそうです。
崋山も幼い頃から、朝4時に起き、炊事の火の明かりで本を読むような生活を送っていました。
弟たちは、少しでも食い扶持を減らすため、奉公に出されたり、寺に預けられたりしました。
後年、崋山は幼い弟を寺に送り出すため、雪の降る中を板橋まで連れていった悲しい別れがあったことを回想しています。
「家族を助けたい」「この貧しさから抜け出したい」。その一心こそが、彼の原動力となっていきました。
「絵で家族を救いたい」——16歳の決意と苦難
こうした逆境の中、崋山は1つの希望を見出します。それは「絵」でした。
彼は幼い頃から絵を描くことが大好きでした。
そして、それ以上に「画家になれば、絵を売って病気の父や母、幼い弟妹たちを助けられるのではないか」と考えたのです。
それは、現代でいう「好きなことを仕事にして、家族を支える」という、切実な決意でした。
幸い、父は息子の決意を理解し、その道を応援してくれます。
16歳になった崋山は、本格的に絵の修業を始めることを決意しました。
しかし、ここでも「貧しさ」が彼の前に立ちはだかります。
絵を習うには、当然ながら師匠への月謝や、画材を買うお金が必要でした。
記録によれば、崋山は最初に入門した師匠のもとで、月謝が払えないばかりか、絵を描くための半紙さえ買えませんでした。
結果として、師匠から破門されてしまうという辛酸もなめています。
扉を開いた情熱。当代随一の画家・谷文晁の懐へ
それでも崋山は諦めませんでした。
絵で身を立てるという決意は、揺らがなかったのです。
彼は、貧しい中でもなんとか武士としての藩務をこなしながら、絵の勉強を続ける方法を探ります。
そして、ついにその扉を開くことになる出会いを果たします。
当代きっての人気画家であり、江戸画壇の大御所であった谷文晁(たにぶんちょう)への入門が許されたのです。
谷文晁は、特定の流派に固執しない、非常に柔軟な考えを持つ画家でした。
日本の伝統的な狩野派や大和絵はもちろん、中国の絵画、さらにはオランダから入ってくる西洋画の技法までをも研究し、自らのスタイルに取り入れる「折衷様式」を確立した人物です。
この師匠との出会いが、崋山の持つ才能と好奇心を、一気に開花させることになります。
学びを止めない探求心。独自の画風を確立した軌跡

谷文晁の塾に入門したとはいえ、崋山の生活がすぐに楽になったわけではありません。
彼は日中、田原藩の武士として藩邸で忙しく働かなければなりませんでした。
絵の勉強に充てられるのは、仕事が終わった後、夜の時間だけです。
彼は、寝る間を惜しんで勉強に打ち込みました。
知人から貴重な絵巻物などを借りては、夜通しそれを模写して技法を学びます。
同時に、生活費を稼ぐための「仕事」としての絵も描き続けました。
例えば、お祭りで売られる凧の絵や、灯籠に描く絵などです。
しかし、崋山はこれを単なる「内職」で終わらせませんでした。
模写で学んだ高度な技術を、生活のための絵で実践し、試行錯誤を繰り返す。
そのすべてを、自らの画力を高める糧にしていったのです。
「すべてを写し取る」——懐のスケッチ帳と「一掃百態図」
崋山の探求心は、師からの学びや模写だけにとどまりません。
彼は、常に懐にスケッチ帳(写生帖)を忍ばせていました。
そして、仕事の合間や移動中、心惹かれる風景や面白い人物に出会うと、時間を見つけてはそれを取り出し、猛烈なスピードでスケッチすることを日課としていました。
「目の前にあるものを、ありのままに写し取る」。この徹底した写実の姿勢こそが、崋山の絵画の真骨頂となっていきます。
その成果がよく表れているのが、彼が26歳の時に描いたとされる「一掃百態図(いっそうひゃくたいず)」です。
これは、当時の江戸の町を行き交うさまざまな人々の姿を描いた、今でいう風俗スケッチ集のような作品です。
そこには、寺子屋で学ぶ子供たち、大名行列の様子、書画の会を楽しむ人々、金魚すくいに興じる庶民など、実に生き生きとした江戸の日常が、ユーモラスかつ軽やかな筆致で描かれています。
驚くべきことに、この多彩な41場面ものスケッチを、彼はわずか3日間で描き上げたと伝えられています。
日頃から膨大な量のスケッチを続け、観察眼を磨き抜いていたからこそ、これほどのスピードとクオリティが実現できたのでしょう。
鎖国下での尽きない好奇心——西洋画法の研究
崋山の好奇心は、国内のものだけには向きませんでした。
彼が最も強く惹きつけられたものの1つが、当時、鎖国下の日本にわずかに入ってきていた「西洋画」です。
師である谷文晁も西洋画に関心を持っていましたが、崋山の情熱はそれ以上でした。
彼は、オランダを通じて入ってくる銅版画(版画)や、ヨーロッパの百科事典の挿絵、さらには舶来の器に描かれた模様さえも、手に入れては熱心に模写し、研究しました。
彼が特に注目したのは、日本の伝統的な絵画にはない2つの技法でした。
1つは「陰影法(いんえいほう)」でした。
これは、光と影を描き分けることで、対象を立体的に見せるテクニックです。
もう1つは「遠近法(えんきんほう)」でした。
これは、遠くのものは小さく、近くのものは大きく描くことで、2次元の紙の上に3次元の空間を生み出す技法です。
「なぜ、西洋の絵はこんなにも本物そっくりに見えるのか?」。その秘密を解き明かそうと、彼は貪欲に新しい知識を吸収していきました。
国宝「鷹見泉石像」の誕生——学びの集大成、東洋と西洋の融合
貧しい家計を助けるために始まった絵の道は、働きながら続けた猛烈なスケッチと、西洋への尽きない探求心によって、ついに奇跡のような一枚の肖像画として結実します。
それが、彼の最高傑作であり、近代日本絵画の幕開けを告げたとさえいわれる、国宝「鷹見泉石像(たかみせんせきぞう)」です。
この肖像画に描かれている鷹見泉石は、蘭学(らんがく)という西洋の学問を通じて崋山と親交のあった、下総国古河藩(しもうさのくにこがはん)の家老でした。
この肖像画が描かれたきっかけは、ある公式な行事にありました。
泉石が、主君の代理として浅草の誓願寺(せいがんじ)へ参拝した際、その正装姿を見た崋山が強い感銘を受け、写生したことが始まりと伝えられています。
単なる依頼で描かれたというよりは、蘭学の先輩であり、尊敬する泉石の威厳に満ちた姿を、画家としてどうしても描き留めておきたいという、崋山の強い創作意欲の表れだったのかもしれません。
写真かと見まがうほどのリアリティ、そして描かれた人物の息遣いや内面までもが伝わってくるような、圧倒的な筆力。
この絵がなぜ「国宝」として高く評価されているのでしょうか。
それは、彼がそれまで学んできた東洋と西洋の技法が、完璧なバランスで融合しているからです。
まず、描かれた人物、鷹見泉石の「顔」には、西洋画の陰影法が巧みに取り入れられ、頬の丸み、鼻の高さ、そして肌の柔らかな質感までが、まるでそこに本人がいるかのように立体的に表現されています。
目元のシワや、頬にあるホクロの1つ1つまで、一切の妥協なく克明に写し取られています。
しかし、ただリアルなだけではありません。
この絵のすごさは、泉石という人物の、実直で知的な「内面性」や「人柄」までもが、その表情から深く伝わってくるところにあります。
一方で、彼が身につけている衣服に目を移してみましょう。
こちらは、顔とは対照的に、東洋の伝統的な画法が用いられています。
素早く、迷いのない伸びやかな筆の線で、パリッとした着物の質感が表現されています。
顔には西洋由来の緻密な立体表現が施され、着衣には東洋由来の大胆な線描が見られます。
この2つがまったく違和感なく1つの画面に収まり、人物の存在感を際立たせているのです。
崋山は、1つの作品を完成させるために、労を惜しまず何枚も何枚も下描きを重ねたといいます。
この「鷹見泉石像」もまた、彼の徹底した観察眼と、たゆまぬ技術の研鑽があったからこそ生み出された、まさに「奇跡の一枚」なのです。
「大功は緩にあり」——日々の積み重ねこそが道を拓く

渡辺崋山は、生前、「大功は緩にあり(たいこうはかんにあり)」という言葉を残しました。
これは、「偉大な功績は、長い時間をかけた地道な積み重ねの末に、ようやく成し遂げられる」という意味です。
布団もないほどの貧しい生活の中、藩務という多忙な本業の傍らで続けた絵の修業。
彼の画業は、まさしくこの言葉を体現したものでした。
どんな逆境にあっても「描くこと」「学ぶこと」を手放さなかったのです。
彼の生き方は、日々の生活や仕事に追われる私たちにも、大切なヒントを与えてくれます。
もし今、何か学びたいことや、磨きたいスキルがあるのなら、焦る必要はありません。
崋山のように、1日10分のスケッチでも、寝る前の30分の読書でもいい。
その小さな積み重ねが、5年後、10年後、きっと自分でも想像しなかったような「大きな成果」となって、人生を豊かに彩ってくれるはずです。
崋山の絵が今なお私たちの心を打つのは、その卓越した技術だけでなく、絵に込められた彼のひたむきな情熱と、弛まぬ努力の軌跡が、私たちに静かな勇気を与えてくれるからなのかもしれません。
人生の目的が5ステップで分かる
特典つきメールマガジンの登録は
こちらから


